めっきのひろば > めっきっていつからあるの?
めっきっていつからあるの?
古代のめっき技術

めっき技術の起源は、紀元前の古代文明に遡ることができます。古代エジプトやメソポタミア、ギリシャ、ローマなどでは、金属の表面に貴金属を薄く施す技術が存在していました。融点の低いスズを溶かして塗布する方法は、人類のめっき史においての原点の一つと言えるでしょう。また、装飾品や宗教的な儀式に使われる物品に金や銀をめっきする技術も普及し、これらがめっき技術の原型となりました。
近代のめっき技術の発展
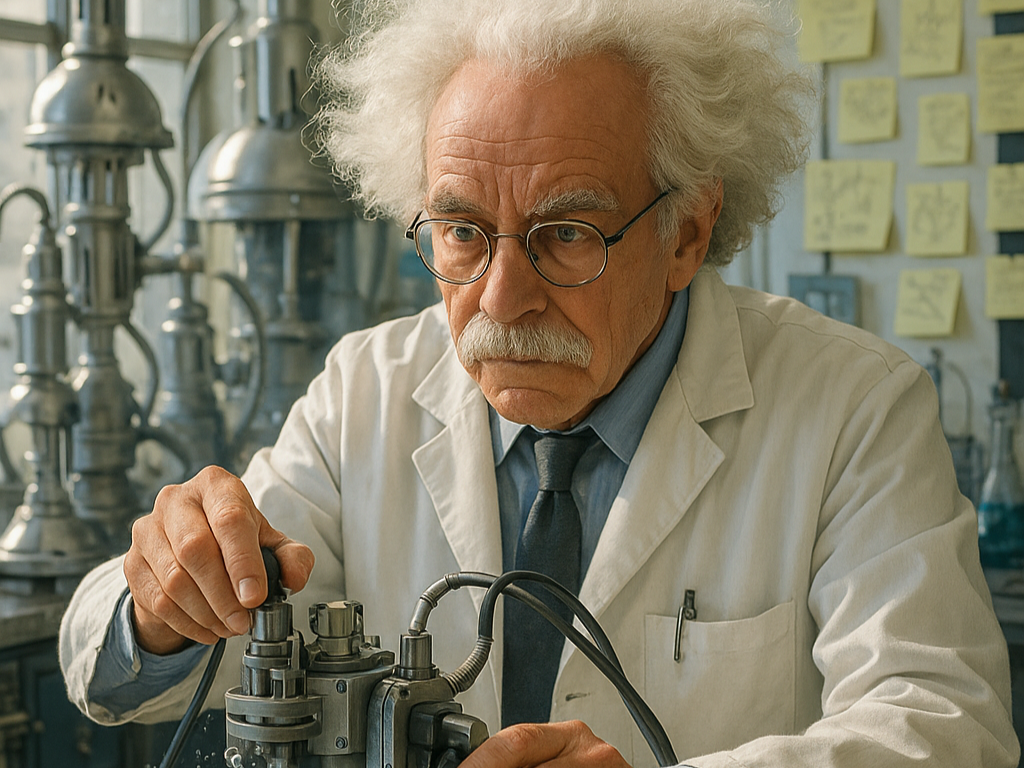
産業革命期(18世紀後半から19世紀)において、めっき技術は大きな進展を遂げました。特に、1800年にアレッサンドロ・ボルタがボルタ電池を発明したことが、電気めっき技術の発展に寄与しました。その後、1830年代から40年代にかけて、電気めっきの技術が開発され、産業界に広まりました。
19世紀中頃、イギリスのバーミンガムにあるエルキントン商会が1840年に電気金・銀めっきの特許を取得し、商業生産を開始しました。これにより、めっき技術は装飾品だけでなく、産業用途にも広がりを見せました。
電気めっきの発明

電気めっきの発明は、めっき技術に革命をもたらしました。1805年にイタリアのルイジ・ヴァレンティノ・ブルニャテッリが、電気を使って金属を析出させる方法を発見し、これが電気めっき技術の原型となりました。この発見は、めっきの精度を飛躍的に向上させ、工業的な生産において広く応用されることになりました。
19世紀後半には、電気めっき技術が工業的に発展し、電解液の改良や電流制御の進歩により、金属表面に均一で高精度なめっき膜を形成することが可能となりました。これにより、金属の外観を美しく仕上げるだけでなく、耐腐食性や耐摩耗性を向上させる技術として重要性を増していきました。また、この時期には無電解めっきの技術も発展し、金属以外の基材に対してもめっきを行うことができるようになりました。










