めっきのひろば > 摺動部とは?①
摺動部とは?①
摺動部について解説!
機械の内部では、部品同士が滑り合いながら動作する「摺動部(しゅうどうぶ)」が数多く存在します。たとえば、軸と軸受け、ピストンとシリンダーなどは、代表的な摺動部です。これらの部位では常に摩擦が発生し、部品の摩耗や精度低下、エネルギー損失の原因となってしまうため、摺動性を高めることは機械の性能維持や寿命延長に直結する重要な課題です。
当記事では、摺動部と可動部・摺動面の違いや、摺動部品の具体例、摺動性を高める方法、効果的な表面処理の種類など、機械設計や保守に欠かせない基礎知識を詳しく解説します。これから機械設計に関わる方や、摺動性の改善に取り組む技術者の方はぜひ参考にしてください。

摺動部とは?
摺動部(しゅうどうぶ)とは、機械内部で部品同士が相対的にこすれ合いながら滑る部分を指します。軸と軸受け、ピストンとシリンダー、レールと可動体などが摺動部の例です。
このような摺動部では、動作中に摩擦が発生します。摩擦は部品の劣化や精度低下、エネルギー損失の原因となるので、摺動性の確保が重要です。摩擦を低減するために、摺動部には潤滑剤の使用や、摺動性の高い素材、表面処理などの工夫が施されます。
摺動部の適切な設計は、機械の性能維持や寿命延長に直結するため、非常に重要な要素です。
三ツ矢の摺動部に使用されるめっきはこちら
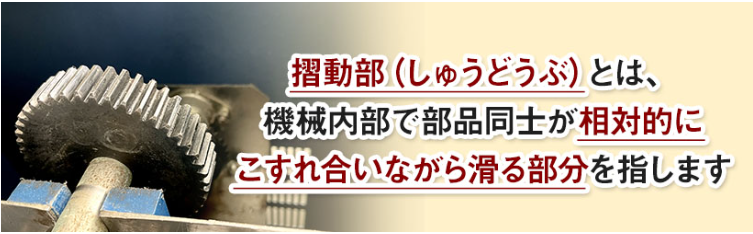
摺動部と可動部の違い
摺動部と可動部は、どちらも機械の動作に関わる要素ですが、定義や性質には違いがあります。
摺動部は、部品同士が直接接触しながら滑るように動く部分であるのに対し、可動部とは「動くことができる部位」の総称です。摩擦の有無や接触の有無にかかわらず、運動機能を持つ部品全体を可動部と呼びます。そのため、間接的な動力伝達によって動く部位も含まれ、摺動を伴わない可動部も存在します。
一方で、摺動部は可動部の一部に含まれる特殊な領域であり、摩擦の影響を考慮する必要があります。
摺動部と可動部を適切に区別すると、部品選定や設計判断の精度が高まり、機械全体の性能や耐久性を向上させることが可能です。
摺動部と摺動面の違い
摺動部と摺動面は類似した用語ですが、機械設計においては用途や意味に明確な違いがあります。
摺動部は軸と軸受け、スライドレールとテーブルなど、機構全体の中で動作時にこすれ合う要素を含んだ「部位」として捉えるのが特徴です。一方、 摺動面は摺動部のうち、実際に互いに接触して滑り合う「面と面の接触部」を指します。たとえば、すべり案内やリニアガイドなどでは、レールとブロックが接する面が摺動面に該当します。
つまり、摺動部は構造全体としての動く部分、摺動面はその中で直接接触し摩擦が発生する具体的な面を指す言葉です。
摺動部品の代表例
摺動部には「回転摺動」「面摺動」「スライド摺動」といった分類があります。回転摺動は軸が回転しながら軸受けと接触する動きで、面摺動は平面同士が滑る動き、スライド摺動は直線的に滑る動きを指します。
摺動性の向上や摩耗対策を考える際は、摺動部品の種類や特徴を正しく理解することが大切です。ここでは、代表的な摺動部品として、ベアリング、ブレード、パッキン、リニアガイド、エンジンシリンダーの5つを取り上げ、それぞれの機能や役割を解説します。

・ベアリング
ベアリング(軸受)は、回転軸を支持しながら摩擦抵抗を低減するための代表的な摺動部品です。摩擦を軽減することでエネルギー効率を高め、部品の摩耗や発熱を抑える役割を担っています。使用される場面は多岐にわたり、自動車や産業機械、家電製品、航空機まで幅広く活用されています。
ベアリングには大きく分けて「すべり軸受」と「転がり軸受」の2種類があります。すべり軸受は軸と軸受の面同士が滑る構造で、潤滑によって摩擦を低減します。一方、転がり軸受は玉やローラーなどの転動体を用いて摩擦を抑えます。
摺動部品としてのベアリングは、機械構造の信頼性や精密性を左右する大切な存在です。
・ブレード
ブレードは、タービンや圧縮機などの回転機械において、流体のエネルギーを効率よく変換・伝達するために使用される摺動部品です。
特にタービンブレードは、高温高圧の蒸気やガスを受けて回転運動を生み出す動翼と、流体の流れを整える静翼とに分かれており、それぞれ高精度かつ高耐久性であることが求められます。これらのブレードは、ジェットエンジン、発電用タービン、真空ポンプなど、過酷な運転条件下で使用されます。材料には耐熱合金が使用され、表面処理や冷却構造によって耐摩耗性と耐熱性が確保されています。
ブレードの設計と摩耗対策は、装置全体のエネルギー変換効率や寿命に直結します。
・パッキン
パッキンは、摺動部における密封機能を担う重要な部品です。主にピストンやバルブ、ポンプなどの可動部に取り付けられ、流体の漏れを防止するとともに異物の侵入を防ぎます。パッキンは常に摺動状態にあるため、摩擦係数が低く、耐摩耗性の高い材質が求められます。使用される素材はゴム、樹脂、繊維、金属などさまざまで、用途や圧力、温度に応じて選定されます。
適切なパッキンを選ぶと、機械の安定稼働とメンテナンス性の向上に効果的です。
・リニアガイド
リニアガイドは、物体をまっすぐに滑らかに移動させるための案内機構であり、摺動部として重要な部分です。直線運動を支える役割を持ち、旋盤や研削盤、供給装置、検査機などに広く用いられています。
一般的なリニアガイドは、レールとキャリッジ(ブロック)から構成され、金属ボールやローラーが循環することによって低摩擦で直線運動を可能にしています。また、高機能樹脂を用いたすべり式リニアガイドも存在し、自己潤滑性とメンテナンス性を両立させています。
リニアガイドは、位置決め精度の向上や長寿命化のために摺動性能と剛性のバランスが重視される部品です。
・エンジンシリンダー
エンジンシリンダーは、ピストンを受け止め、上下運動をガイドする円筒状の構造部品であり、摩擦が発生する代表的な摺動部です。ピストンとの接触面は高圧・高温にさらされるので、耐摩耗性・耐熱性に優れた素材や表面処理が求められます。
エンジンの性能や効率に大きく関わるため、シリンダー内壁にはホーニング加工や表面コーティングなどの処理が施されます。潤滑油の循環も重要で、潤滑不良は焼き付きや摩耗を引き起こします。
エンジンシリンダーの摺動性を高めることは、燃費や出力の向上、排気ガスの抑制にもつながります。
摺動部の摺動性を高める方法
摺動部は、運転条件や用途に応じて設計を最適化する必要があります。たとえば、高温環境下では熱に強い素材や潤滑機構が求められ、高速運転では表面処理による摩耗抑制が不可欠です。
適切な材料選定や表面処理の選択、潤滑設計など、摺動部の特性を的確に把握することが、信頼性の高い機械の実現につながります。
摺動部の摺動性を高めるには、いくつかの手法が存在します。代表的な方法としては、摺動性の高い素材の選定、潤滑剤の使用、部品形状の工夫、そして表面処理の実施が挙げられます。これらの対策は単独でも有効ですが、状況に応じて複数を組み合わせて活用することで、より安定した性能を得られます。
ここでは、摺動性を高める具体的な方法を解説します。
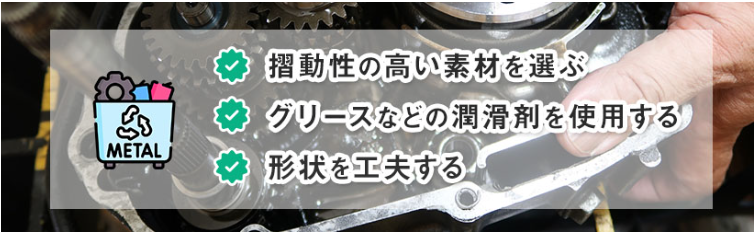
①摺動性の高い素材を選ぶ
摺動性を高める基本的な方法として、摩擦係数が低く、すべりやすい素材を選ぶことが挙げられます。代表的な素材としては、自己潤滑性を持つ樹脂類、テフロン(PTFE)や超高分子量ポリエチレン、MCナイロン、POM、PEEKなどが広く使用されています。これらの素材は動摩擦係数が低く、潤滑剤なしでも滑らかな動作が可能です。
ただし、摺動性の高い素材は、衝撃や高荷重に対する耐性が劣る場合があるので、強度や耐熱性とのバランスを考慮して選定することが大切です。使用環境に適した素材を選べば、メンテナンス頻度の低減や長寿命化が期待できます。
②グリースなどの潤滑剤を使用する
潤滑油やグリースを摺動部に供給することで、金属同士の直接接触を防ぎ、摩擦と摩耗を大幅に低減できます。たとえば、自動車のエンジンではエンジンオイルがこの役割を果たしています。
潤滑剤の選定は、温度や荷重、動作速度など使用条件に応じて行う必要があります。また、潤滑剤の効果を持続させるためには、定期的な補充や交換といったメンテナンス体制も不可欠です。
潤滑剤の適切な使用は、摺動部の機能を最大限に引き出し、焼き付きや異音などのトラブルを未然に防ぎます。
③形状を工夫する
摺動性は、材料だけでなく部品の形状設計にも大きく左右されます。 表面に凹凸があると摩擦抵抗が増えるため、接触面はできるだけ平滑に加工することが大切です。また、接触面積が大きすぎると摩擦が増加するので、面積を適度に抑える工夫も求められます。
たとえば、歯車の設計においては、エッジ部分にアール(曲線)を付けてスムーズな摺動を実現するなど、形状面での最適化が行われています。適切な形状設計により、摩耗を抑えつつ、長期間にわたって安定した摺動性能を維持することが可能になります。
④表面処理を行う
摺動性を向上させる手段として、表面処理も有効です。 材料自体の特性だけでは摺動性が不十分な場合でも、表面に特殊な処理を施すことで性能を補えます。たとえば、硬質クロムメッキや無電解ニッケルメッキは、摩擦係数の低下と耐摩耗性の向上を同時に実現します。
特に金属材料の場合、表面に潤滑性や硬度を付与すると、焼き付きやフレッティング摩耗などのトラブルを防ぐことが可能です。素材選定が難しい場面でも、表面処理を施すことで摺動性を確保し、長寿命化と信頼性向上を両立させられます。










