めっきのひろば > 半田(はんだ)濡れ性とは?
半田(はんだ)濡れ性とは?
はじめに
電子機器の製造やプリント基板の実装において、半田付けの品質は製品の信頼性を大きく左右します。その中でも「半田濡れ性」は、金属表面にどれだけなめらかに広がるかを示す重要な指標です。濡れ性が良好であれば、半田がしっかりと密着し、安定した接合が可能になります。一方で濡れ性が不十分だと、接合不良や導通不良などのトラブルを招く恐れがあります。
当記事では、半田濡れ性の基本から、濡れ性が低下することによる影響、主な要因とその対策、濡れ性を評価する方法について解説します。
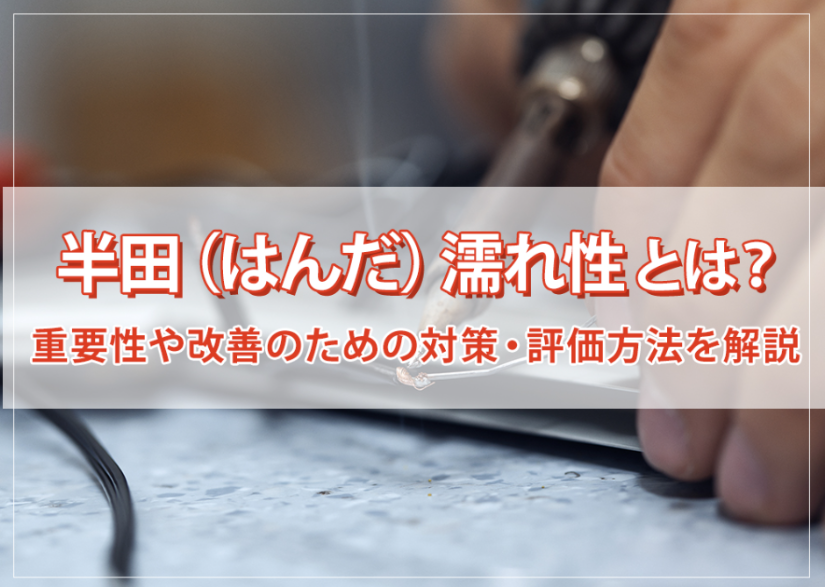
1.半田(はんだ)濡れ性とは
半田濡れ性とは、 半田が金属表面にどれだけ馴染み、滑らかに広がるかを示す特性のことです。製品の組立て工程では、複数の部品を確実に接合する必要があり、このときの濡れ性(または付け性)が接合の品質を左右します。濡れ性が良好であれば、半田は金属表面に均一に広がって密着し、強固かつ信頼性の高い接合が可能です。反対に濡れ性が低いと、半田が弾かれてうまく密着せず、接合不良の原因となります。
この濡れ性は、電子部品の製造やプリント基板の実装といった分野でも極めて重要視されている要素の1つです。半田の種類や温度、下地メッキの材質、部品表面の状態、使用するフラックスの種類や量など、多くの要因が濡れ性に影響します。特に濡れ性が不十分な場合は、接合強度の低下を招き、製品全体の性能や安全性に悪影響を及ぼすおそれがあります。
なお、濡れ性が悪く半田が広がらない状態は「不濡れ不良」と呼ばれます。主な原因には、部品表面の酸化、フラックスの不足、加熱条件の不適切さなどが挙げられます。高品質な半田付けを実現するには、こうした条件を適切に管理することが重要です。
三ツ矢のはんだ濡れ性を付与するめっきはこちら
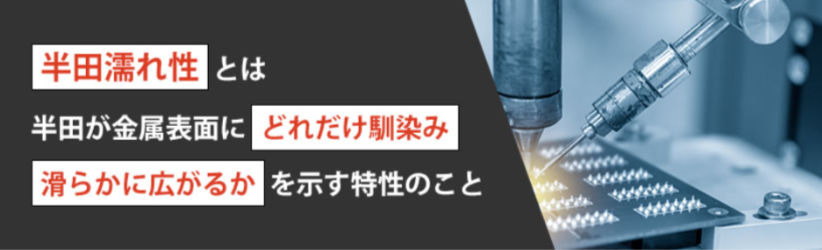
2. 半田濡れ性が低い場合はどうなる?
半田濡れ性が十分でないと、見た目には接合されているように見えても、内部でさまざまな不具合が起きやすくなります。以下では、濡れ性が低いことで発生しやすくなる代表的な問題点について紹介します。
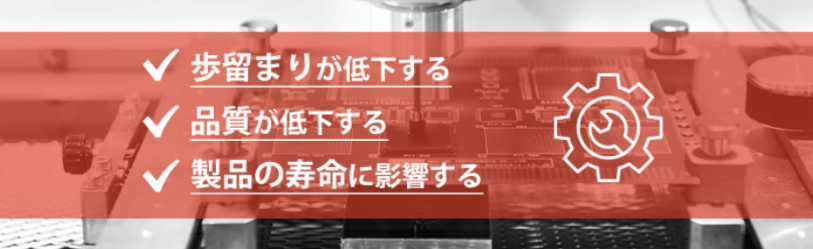
①歩留まりが低下する
半田濡れ性が低い場合、接合不良や半田浮き、ブリッジなどの不具合が発生しやすくなります。これにより製品が基準を満たさず、不良品として排出される割合が増加するため、製造現場では「歩留まり(ぶどまり・yield)」が低下する大きな原因となります。
歩留まりとは、投入した原材料に対して良品として得られた製品の割合を示す指標です。 濡れ性の低下により不良品が多発すると、工程全体の生産効率が落ち、結果としてコスト増や納期遅延にもつながりかねません。特に大量生産を行う電子機器業界などでは、濡れ性の管理が収益を左右する重要な要素となります。
②品質が低下する
半田濡れ性が低いと、製品の品質に悪影響を及ぼすおそれがあります。半田が均一に広がらず接合が不完全になり、導通不良や剥離が起きやすくなるためです。
たとえば、半田が馴染まない「イモはんだ」や、接合部に亀裂が入る「クラック」、熱不足によって生じる「冷接点」などは、いずれも信頼性の低い接点とみなされます。これらの不良は、 加熱不足や作業環境など複数の要因が関与しますが、半田濡れ性の低さも発生要因の1つとして関係しています。
半田の不良は、製品の誤作動や故障を引き起こすおそれがあり、品質全体の低下を招きます。また、検査をすり抜けた不良が出荷後に発覚すれば、企業の信用にも関わる重大な問題となりかねません。
③製品の寿命に影響する
半田濡れ性が低いと、接合部が不安定になり、製品の寿命に悪影響を及ぼします。濡れ性が悪いままでは、 温度変化や振動によってクラック(亀裂)が入りやすくなり、長期使用で断線や故障を引き起こす可能性があるためです。
信頼性評価では、ヒートサイクル試験(TCT)によって接合部の耐久性が確認されます。濡れ性が良好であれば、接合が安定し、試験後も長期にわたり使用に耐える製品が実現できます。一方、濡れ性が不十分だと、初期の劣化が早まり、寿命の短縮につながるおそれがあります。製品の信頼性を保つためには、濡れ性の管理が重要な要素の1つです。
3. 半田濡れ性に影響する主な要因と対策
半田濡れ性は、単に作業手順や技能だけで決まるものではありません。基板や部品の表面状態、使用するフラックスや半田の成分、加熱条件など、複数の要因が複雑に関係しています。ここでは、濡れ性に影響を及ぼす代表的な要素と、それぞれに対する基本的な対策を解説します。
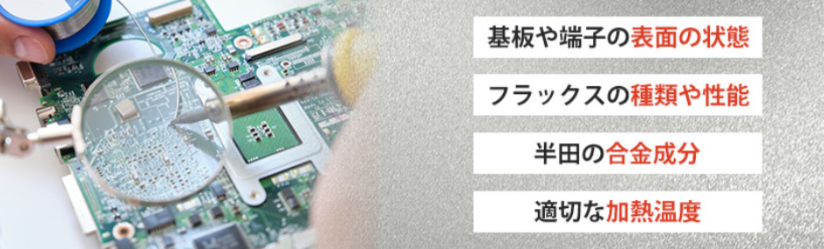
1.基板や端子の表面の状態
半田濡れ性において、基板や端子の表面状態は非常に重要です。 酸化膜や汚れがあると、半田がうまく広がらず濡れ性が低下します。特に銅やニッケルは酸化しやすく、濡れにくい傾向があります。対策としては、金メッキや銀メッキなど濡れ性に優れた表面処理を施すことが有効です。また、保管時には酸化を防ぐ工夫や、実装前に適切な洗浄を行うことも濡れ性改善に役立ちます。
2.フラックスの種類や性能
半田濡れ性を確保する上で、フラックスの選定と性能は極めて重要です。フラックスは金属表面の酸化物を除去し、半田の広がりを助ける役割を担います。活性度の高いフラックスを使用すれば、酸化の進んだ表面でも濡れ性を高められる可能性があります。
ただし、強すぎる成分は腐食の原因にもなり得るため、 基材や用途に応じた適切な種類(RMA・RA・水溶性など)を選ぶことが大切です。また、塗布量や塗布方法にも注意が必要で、過不足によっては濡れ性の低下を招く恐れがあります。
3.半田の合金成分
半田の濡れ性は、含まれる金属の組成によって大きく左右されます。たとえば、従来使われていたスズ鉛合金(Sn-Pb)は濡れ性に優れ、滑らかに広がる特性があります。しかし、鉛は人体や環境への悪影響が懸念され、現在では鉛フリー半田(Sn-Ag-Cuなど)が主流です。
ただし鉛フリー半田は、鉛入りと比べて濡れ性が劣る傾向があり、適切な加熱条件やフラックスとの併用が必要になります。 合金成分の違いを理解し、使用目的に合った半田を選定することが濡れ性改善のポイントとなります。
4.適切な加熱温度
半田濡れ性を確保するには、適切な加熱温度と加熱プロファイルの管理が不可欠です。温度が低すぎると、半田が十分に溶けず、基板表面にうまく広がりません。一方で、温度が高すぎると、部品や基板の酸化が進み、濡れ性を損なうおそれがあります。
加熱プロファイルでは、予熱・リフロー・冷却の各段階を適切に制御し、半田がなめらかに広がるように設定することが重要です。温度と時間のバランスを取ることで、安定した接合が可能になります。
4. 半田濡れ性の評価方法
半田濡れ性を正確に評価するには、客観的な測定方法が大切です。接合の品質を確保するために、業界ではさまざまな評価方法が用いられています。代表的な手法として「接触角測定」「スプレッドテスト」「ウェッティングバランステスト」があり、それぞれ異なる角度から濡れ性の良否を確認できます。
以下では、それぞれの評価方法の特徴を解説します。
①接触角測定
接触角測定は、 半田が金属表面にどれだけ広がるかを数値で評価する代表的な方法です。溶融半田を金属表面に滴下し、半田の輪郭と基板との間にできる角度(接触角)を測定します。接触角が小さいほど濡れ性が高く、よく広がっていることを示します。一方で、角度が大きいと濡れ性が低く、半田が広がりにくい状態と判断されます。定量的な比較が可能なため、材料や条件ごとの濡れ性評価に広く活用されています。
②スプレッドテスト(広がり試験)
スプレッドテスト(広がり試験)は、半田の濡れ性を評価する基本的な方法の1つです。 一定量の半田とフラックスを金属板上に置き、所定の温度と時間で加熱した後、半田がどの程度広がるかを測定します。広がり面積や広がり率などを評価指標として使用し、濡れ性の良否を判断します。
特に、材料やフラックスの違いによる濡れ性の比較に有効です。広がりが大きいほど、金属表面に対して良好な濡れ性があると評価されます。
③ウェッティングバランステスト(平衡法)
ウェッティングバランステスト(平衡法)は、半田濡れ性を数値で定量的に評価できる試験方法です。 金属サンプルを一定温度の半田槽に垂直に浸漬し、半田が金属表面を引き上げる力(濡れ力)の変化を時間ごとに測定します。
ウェッティングバランステストにより、濡れ始めるまでの時間(ウェットタイム)や最大濡れ力が得られ、濡れ性の良否を客観的に判断できます。工程管理や品質保証の場面で広く用いられており、JISやIPCなどの国際規格にも準拠した試験です。
まとめ
半田濡れ性とは、半田が金属表面にどれだけ馴染み広がるかを示す特性で、電子部品の接合品質を左右する重要な要素です。濡れ性が低いと接合不良が発生し、歩留まりや品質の低下、製品寿命の短縮につながります。
濡れ性に影響する主な要因として、基板表面の状態、フラックスの種類、半田の合金成分、加熱温度などがあります。特にメッキ素材は濡れ性に大きく関係しており、金や銀などの表面処理は良好な濡れ性を示す一方、酸化しやすい銅やニッケルは注意が必要です。評価方法には接触角測定、スプレッドテスト、ウェッティングバランステストがあり、これらにより客観的な濡れ性評価が可能です。
三ツ矢では、電気的接合特性に適した多様なメッキ処理を提供しています。金や銀はもちろん、コストや耐久性を考慮したロジウムめっきや硬質銀めっきも取り扱いがあり、それぞれの用途や条件に応じた最適な提案が可能です。半田付け品質の向上やコストバランスをお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
はんだ濡れ性を付与するめっきについてのお問い合わせはこちら










