めっきのひろば > プリント基板への銀メッキとは
プリント基板への銀メッキとは
はじめに
プリント基板は電子機器の心臓部であり、回路を正確に機能させるためにメッキ処理が不可欠です。メッキは単に金属を覆う工程ではなく、導電性や接続性を高め、はんだ付け性や耐食性を確保する重要な役割を担います。
当記事では、プリント基板におけるメッキの目的と銀メッキをはじめとした代表的なメッキの種類、各処理のメリットと注意点について詳しく解説します。プリント基板への処理について詳細を知りたい方はぜひご覧ください。
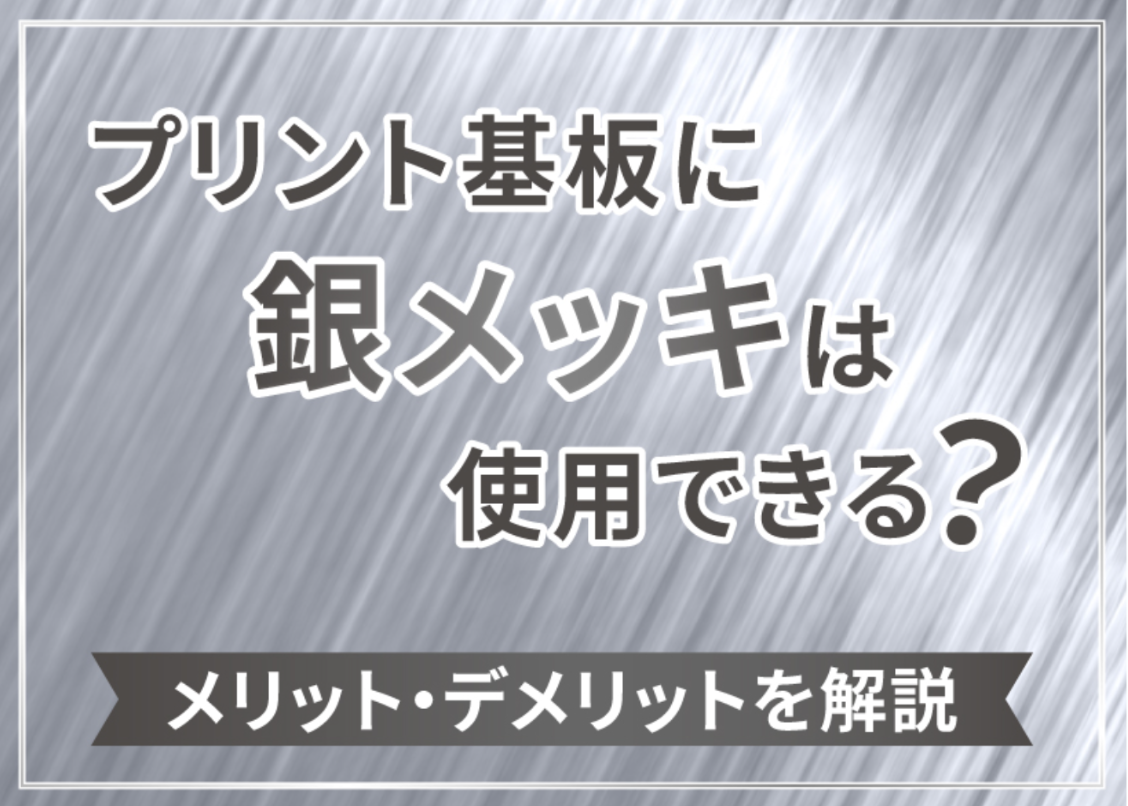
1.プリント基板(PCB)へのめっきとは
プリント基板の製造では、メッキが欠かせません。ここでは、導電性・接続性・はんだ付け性・耐食性といった観点から、プリント基板にメッキを施す理由を詳しく解説します。
1.導電性を付与するため
プリント基板の絶縁基材に開けたスルーホールやビアへ電気を通すには、孔壁へ連続した金属皮膜を形成する必要があります。 メッキを施すことで非導電面に初期導電層を付与し、内層と外層、層間同士が低抵抗で接続され、多層基板の信号経路や電源配線が成立します。
さらに、表面の端子やランドに適切なメッキを施すと、微小電流から大電流まで安定した導通が得られます。銀や金などの貴金属は比抵抗が低く酸化に強いため、高周波や微小信号の劣化抑制にも有効です。
2.接続性を高めるため
電子部品と基板を正しく接続するには、表面の状態が安定していることが重要です。銅はそのままでは酸化しやすく、接触抵抗が大きくなるため、部品との接続が不安定になります。そこで、 表面にニッケルや金、銀などをメッキして、酸化を防ぎつつ接続性を確保します。
金は特に酸化に強く、半導体チップとのワイヤーボンディングに適しています。また、コネクタ端子など摩耗が多い部分では、硬質金やニッケルを組み合わせて耐久性を高めます。適切なメッキ処理を行うことで、接続不良を防ぎ、長期使用でも安定した信号伝達が可能になります。
3.はんだ付け性を上げるため
はんだ付けの品質は、金属表面の「濡れやすさ」に左右されます。銅は空気中で酸化しやすく、酸化膜ができると溶けたはんだが広がらず、接合が弱くなります。そこで、 表面に金や銀、錫などをメッキすることで、酸化の進行を防ぎつつ、はんだが均一に広がるようにします。
ENIG(無電解ニッケル/金メッキ)や無電解銀処理などは、微細なランドにも対応でき、実装時の不良を減らせます。部品が基板にしっかり固定され、電気的にも機械的にも信頼性の高い接合が実現します。
量産における歩留まり向上にも直結するため、メッキ処理は実装工程に欠かせません。
4.錆を防止するため
プリント基板の表面にある銅は薄く、空気や湿気と接触するとすぐに酸化してしまいます。酸化銅は電気を通しにくく、はんだ付けや接続の不良につながります。これを防ぐため、基板にはソルダーレジストを塗布し、必要な接続部分だけを露出させます。
露出部分には金や銀、錫などでメッキを行い、酸化を防ぐと同時に次の実装工程でも安定した性能を発揮させます。さらに、完成した基板は真空包装や乾燥環境で保管され、酸化の進行を最小限に抑えます。こうした対策によって、基板は長期間にわたって信頼性を保ち、製品全体の耐久性向上につながります。
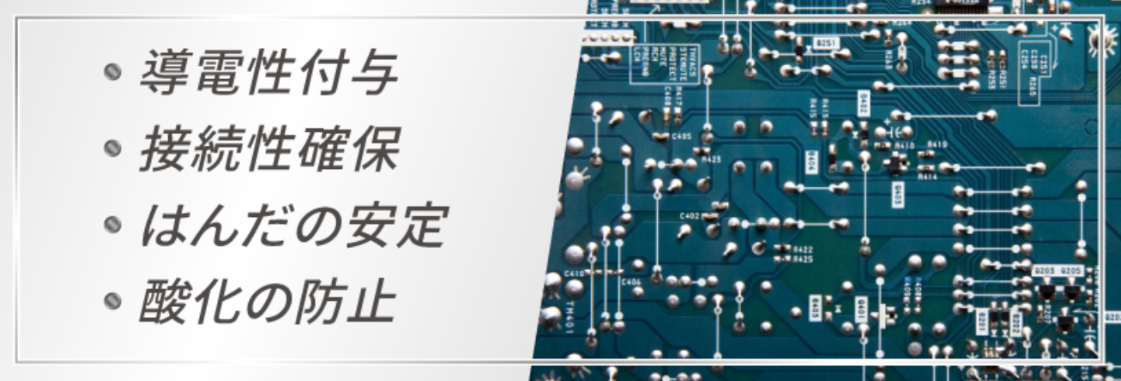
2.銀めっきとは
プリント基板では、用途に応じて複数の表面処理が使われます。代表例の1つが銀メッキです。銀の薄い皮膜を基板表面に形成する銀メッキでは、導電性や実装適性といった機能が付与できます。
ここでは、銀メッキの特徴としてメリットとデメリットを紹介します。
三ツ矢の銀めっきはこちら
1.銀メッキのメリット
銀メッキの最大の利点は、はんだ付け性とボンディング性の高さです。銅は表面が酸化すると濡れにくくなりますが、銀皮膜は初期の濡れ広がりが良好で、微細パッドでも均一なフィレット形成を助けます。ワイヤーボンディングや端子の圧接でも界面の初期接触が安定しやすく、工程ばらつきの吸収に役立ちます。
もう1つの強みは導電性です。銀は金属の中でも非常に低い抵抗率を持ち、接触抵抗の上昇を抑えやすい特性があります。さらに、無鉛実装との相性も良く、再リフロー時の濡れ再現性や外観の安定にもプラスに作用します。
適切な厚み管理と前処理を組み合わせることで、量産における実装歩留まりと電気特性の両立が期待できます。
2.銀メッキのデメリット
銀メッキ加工によるデメリットは、酸化・硫化による変色と特性劣化が起きやすい点です。銀は空気中の硫黄化合物と反応して硫化銀皮膜を生じやすく、表面が黒変します。接触抵抗やはんだ濡れを悪化させ、長期保管後の実装不良や接触不良の原因となります。高湿度と硫黄成分が同時に存在する環境では、いわゆるクリープ腐食や表面マイグレーションが生じ、微小導通の不安定化を招くおそれもあります。
量産が必要な現場では、アンチターニッシュ処理、乾燥剤や窒素封入、真空包装、低温低湿での保管といった運用管理が欠かせません。ENIGと比べて保管許容期間が短くなりやすいので、実装までのリードタイム管理や開封後の取り扱いルールも必要です。

3.プリント基板で使われるその他のめっき
プリント基板では、用途に応じて表面のメッキ処理を使い分けます。代表的なのが金・銅・ニッケルの各メッキです。ここでは、それぞれの特性と採用場面、設計時に意識したいポイントを整理します。
①金めっき
金メッキは、接触部や実装パッドの信頼性を高める目的で用いられます。
代表例のENIG(無電解ニッケル/置換金)は、ニッケル下地が銅の拡散を抑え、表層の金が酸化を防ぎます。平坦性が高く、BGAなどの微細実装に適します。
コネクタの端子や基板エッジのゴールドフィンガーでは、摩耗に強い硬質金(電解金)を使うことが多く、挿抜による接触抵抗の上昇を抑えられます。ワイヤーボンディングでは金表面が有利に働き、初期接触が安定します。
金メッキの注意点はコストと仕様選定です。必要部位のみに限定した部分メッキや、目標膜厚・ニッケル/金の組み合わせを適切に決め、性能とコストのバランスを取る必要があります。
三ツ矢の金めっき
②銅めっき
銅メッキは、基板の導電経路を形成するために欠かせないプロセスです。特にスルーホールやビアの内部に無電解銅を析出させ、その後電解銅で膜厚を確保する工程は、多層基板の配線接続に不可欠です。
銅は導電性と熱伝導性に優れており、電気信号の伝送効率や放熱性能を高める役割を果たします。さらに、銅メッキは上層の金やニッケルメッキの下地としても活用され、密着性を強化します。
ただし、銅は酸化しやすいため、その後のソルダーレジストや表面処理による保護が必須です。
三ツ矢の銅めっき
③ニッケルめっき
ニッケルメッキは、主に拡散バリアや耐摩耗性の向上を目的に使われます。
ENIGでは銅と金の間にニッケルを配置することで、銅の拡散を抑え、はんだ食われや接触抵抗の悪化を防ぎます。摩擦にも強いため、コネクタ端子やスイッチ部品など頻繁に動作する部位にも採用されます。
電解ニッケルは比較的低コストで処理できる反面、形状によって膜厚にムラが出やすいという課題があります。無電解ニッケルは均一性に優れますが、薬品コストが高く条件管理も難しいため、用途や製品の要求特性に応じた選定が必要です。
三ツ矢のニッケルめっき

まとめ
プリント基板に施されるメッキは、単なる保護膜にとどまらず、電子機器の性能と寿命を大きく左右する要素です。導電性の確保や接続信頼性の向上、はんだ付け性の改善、酸化防止など、多面的な機能を持つことから、用途や設計条件に応じて適切な処理方法が選択されます。
たとえば、銀メッキは高い導電性と実装適性を備える一方、硫化による変色リスクがあるため保管管理が必須です。金やニッケルの組み合わせは、耐摩耗性や拡散バリアとしても有効です。
適切なメッキ選定と管理を行うことで、プリント基板は長期にわたって安定動作し、製品全体の品質と信頼性を高められるでしょう。
プリント基板へのめっきに関するお問い合わせはこちら










