めっきのひろば > かじりとは?①
かじりとは?①
はじめに
金属部品の使用現場では、「かじり」と呼ばれるトラブルがしばしば発生します。これは、金属同士が摩擦によって凝着し、滑りが妨げられる現象です。ねじやベアリングなどの摺動部では特に注意が必要で、場合によっては部品の破損や脱着不能といった深刻な問題に発展することもあります。
特にステンレスやアルミ、チタンなどの金属は、延性が高く摩擦熱の影響を受けやすいため、かじりを起こしやすい傾向があります。
当記事では、かじりのメカニズム、発生しやすい条件、代表的な金属の特徴、予防策や効果的なめっき処理などを解説します。金属部品の信頼性を高めたい技術者や設計に関わる方は、ぜひご覧ください。
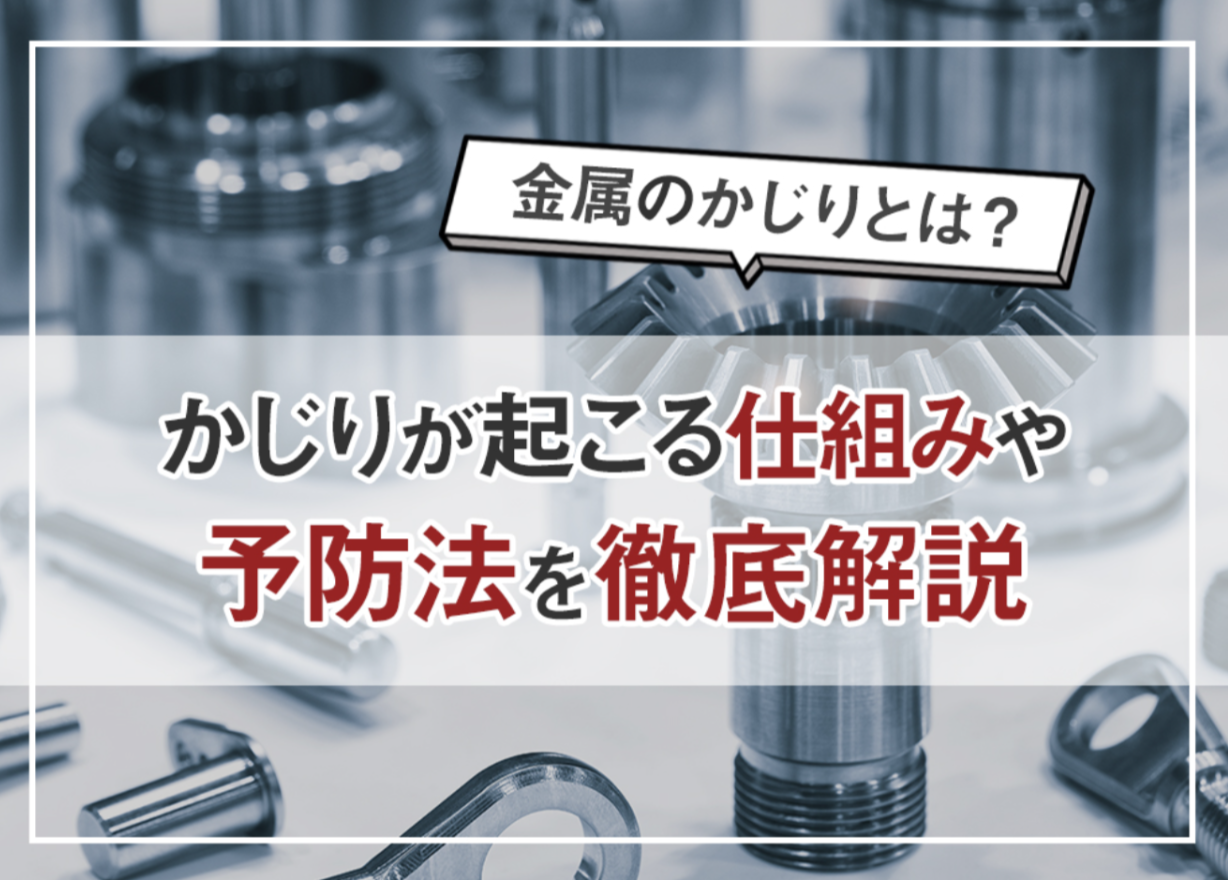
1.金属の「かじり」とは
金属の「かじり」とは、金属同士が高い圧力で接触し、摩擦を受けることで表面同士が凝着し、滑りが阻害される現象を指します。
主にねじやベアリング、摺動部品などの接触面で発生しやすく、構成部品の破損や脱着困難などの不具合につながります。
特にステンレス鋼やアルミニウム、チタンなどの金属では、表面硬度が近く潤滑性も低いため、かじりが起こりやすい傾向があります。
製品設計や保守において、かじりのリスクを理解し、適切な対策を講じることが信頼性向上のために大切です。
三ツ矢の耐かじり性を持つめっき
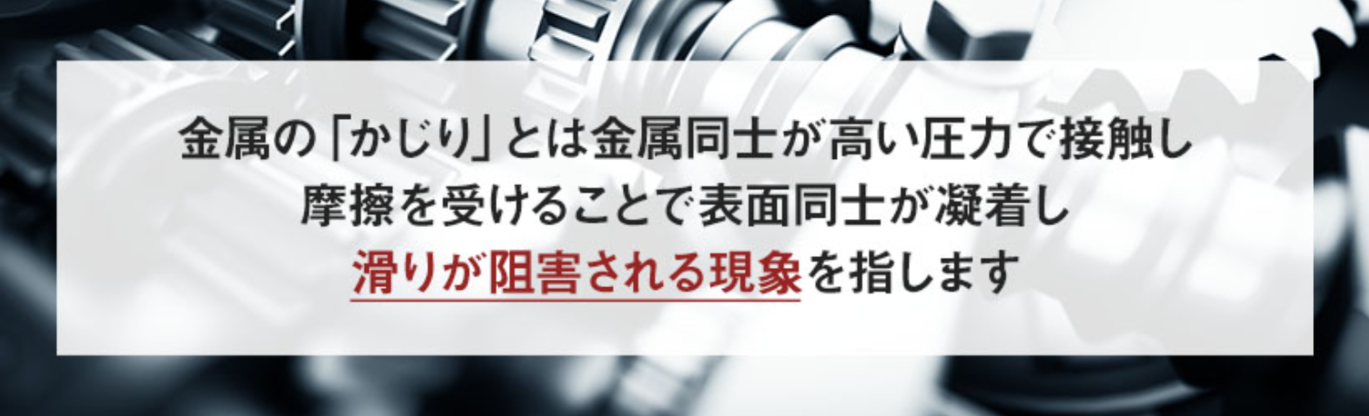
2.金属のかじりが起こる仕組み
金属のかじりは、複数の要因が重なることで発生します。 部品の材質や表面状態、使用環境などによって、かじりの発生リスクは大きく左右されます。ここでは、かじりの主な発生要因について詳しく解説します。
①表面保護が十分ではない
金属表面が酸化皮膜やコーティングなどで適切に保護されていない場合、かじりのリスクが高まります。特に高圧下で使用されるねじや摺動部品では、摩擦によって保護層が削り取られ、素地金属が露出することがあります。露出した金属同士が接触すると、微小な金属の移動や冷間圧接を誘発します。
特にステンレス鋼のような不動態皮膜をもつ金属は、酸化層の破壊によって急激に凝着し摩耗が進行しやすいため、適切な表面処理や潤滑の選定が重要です。
②接触面にごみが挟まった
部品同士の接触面に、金属粉や削りくず、研磨材などの異物が挟まると、かじりが発生しやすくなります。こうした異物は「デブリ」とも呼ばれ、摩擦面に強い局所的圧力をかけることにより、表面を傷つけたり、酸化膜を破壊したりします。
製造現場や組立作業では、清浄な作業環境を保ち、異物混入のリスクを最小限に抑えることが求められます。特に高速摺動部品や精密機構では、微細な粒子であっても重大なかじりの要因となり得ます。
③負荷が大きすぎる
過大な荷重が金属部品にかかると、接触面の摩擦が増加し、局所的な温度上昇や材料の変形を引き起こします。高い締結トルクが必要とされる構造や高荷重がかかる摺動面では、摩耗だけでなく冷間溶着によるかじりも生じやすくなります。
特に高負荷下では、潤滑剤の効果も低下しやすくなるので、荷重の最適化や部品強度の適切な設計によって、かじりのリスクを制御することが大切です。
④腐食や摩耗が起きている
金属部品が腐食や摩耗によって表面損傷を受けている場合、保護層が失われてかじりが発生しやすくなります。特に屋外や高湿度環境で使用される機器では表面状態が劣化し、摩擦抵抗が増加します。摩耗によって表面が粗くなると、微細な突起が形成され、局所的に圧力が集中しやすくなり、凝着摩耗の進行が促されます。
防錆処理や摩耗対策を怠ると、かじりによる早期トラブルが発生する可能性があるため、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。
⑤振動や衝撃で接触状態が変わった
振動や衝撃によって部品の接触状態が一時的に変化すると、瞬間的に圧力や摩擦が集中し、かじりが発生することがあります。特にボルトやナットなどの締結部品では、振動により緩みが生じ、摩擦面が不安定になることが多く、微動摩耗(フレッチング)による酸化皮膜の損傷や凝着が進行します。
また、衝撃荷重を受ける部品では、短時間に高い力が加わるため、表面保護膜が破壊され、金属同士の直結が生じやすくなります。振動対策や緩み止めの工夫によって、かじりの抑制が可能です。
⑥高温環境で作業している
高温環境では、金属が軟化しやすくなるため、通常の温度条件下よりも凝着や摩耗が進行しやすくなります。高温での摩擦により金属表面が溶着し、かじりを引き起こすことがあります。さらに、潤滑剤の性能も温度上昇によって劣化するため、保護効果が低下し、金属間の直接接触が発生します。
特に蒸気や高熱を伴う設備、焼結部品や鋳造品の仕上げ工程などでは、高温によるかじり対策が必要です。耐熱潤滑剤の使用や断熱設計の工夫によってリスクを軽減できます。
3.金属のかじりの種類
金属のかじりは、その発生メカニズムに応じていくつかの種類に分類されます。ここでは代表的な5つのかじりの種類について、かじりの特徴や発生原因を解説します。
①アブレシブ摩耗
アブレシブ摩耗とは、摺動面において硬い物体や異物が相手材の表面を引っかくようにして削り取る摩耗現象です。アブレシブ摩耗は大きく2種類に分類されます。1つ目は「二元アブレシブ摩耗」で、硬い金属の突起が柔らかい相手材を直接削るものです。2つ目は「三元アブレシブ摩耗」で、金属間に挟まった硬い粒子(粉塵や研削くずなど)が原因となり、両者の表面を傷つけながら摩耗を進行させます。
さらに、液体の流れに含まれる粒子が衝突して表面を損傷する「スラリー摩耗」や、液体そのものの衝突による「エロージョン」もアブレシブ摩耗の一種に含まれます。アブレシブ摩耗は一度発生すると急速に進行するため、清浄な環境の維持や異物の混入防止が欠かせません。
②凝着摩耗
凝着摩耗は、摺動する金属表面同士が高温や高圧によって局所的に癒着し、その後の運動によって凝着部分が引き剥がされ、摩耗が進行する現象です。いわゆる「焼き付き」とも呼ばれ、最も基本的かつ深刻なかじりの形態とされています。
同一材料同士や結晶構造が類似する金属同士は、凝着しやすい傾向があります。摩擦熱が表面温度を上昇させ、酸化皮膜が破れた箇所で金属原子が接合し、冶金的な結合が発生します。一度凝着が生じると摩擦抵抗が急激に増大し、部品破損や作動不良を引き起こす原因になります。潤滑剤の選定や異種金属の組み合わせが有効な対策です。
③疲労摩耗
疲労摩耗は、繰り返される接触や荷重の変動によって金属材料が疲労し、微細な割れや剥離が生じて進行する摩耗です。この現象は「ピッチング」「フレーキング」「ピーリング」とも呼ばれ、摩擦面にうろこ状の剥離や小さな穴が現れることが特徴です。
材料の表面は、繰り返しの荷重によって硬化し、応力が集中しやすくなります。その結果、表面に微細な亀裂が発生し、やがて剥離や崩壊につながります。対策としては、材料強度の向上や応力分散設計が有効です。
④フレッチング摩耗(微動摩耗)
フレッチング摩耗とは、金属同士が微小な振幅で繰り返し擦れ合うことによって発生する摩耗現象です。「微動摩耗」や「微摺動摩耗」とも呼ばれ、振動や熱膨張による微細な動きが原因となります。接触部に局所的な高温が発生し、酸化・腐食が進行することが特徴です。
赤錆の発生を伴うことが多く、接触面の疲労強度が著しく低下します。放置すると、疲労破壊や亀裂の進展によって重大な機械的故障につながるおそれがあります。微動摩耗の対策としては、固体潤滑剤の使用や、接触面の固定による相対運動の抑制などが挙げられます。
⑤腐食摩耗
腐食摩耗は、金属表面が化学的腐食と機械的摩耗を同時に受けることで進行する摩耗です。潤滑剤の劣化によって発生した酸性物質や、環境中の水分・化学薬品によって金属表面が腐食されると、強度が低下しやすくなります。その状態で摩擦が加わると、表面が次々に削れ、摩耗が加速します。
この現象は特に湿潤環境や高温・高湿の条件下、腐食性雰囲気中での運転で顕著に現れます。腐食と摩耗が交互に繰り返されるため、進行速度が速く、表面の劣化を招きます。対策としては、耐食性材料の使用や、潤滑剤の定期交換が効果的です。










