めっきのひろば > 建浴とは?役割や基本工程を解説
建浴とは?役割や基本工程を解説
建浴とは?
めっきや表面処理の品質を維持・向上させる上で必要なのが「建浴」です。建浴とは、処理液が劣化した際や新たに処理ラインを立ち上げる際に、所定の薬品を配合して新たな処理液を作る作業のことを指します。処理の種類や使用環境によって建浴のタイミングや方法は異なり、適切な薬品の選定や濃度管理が求められます。
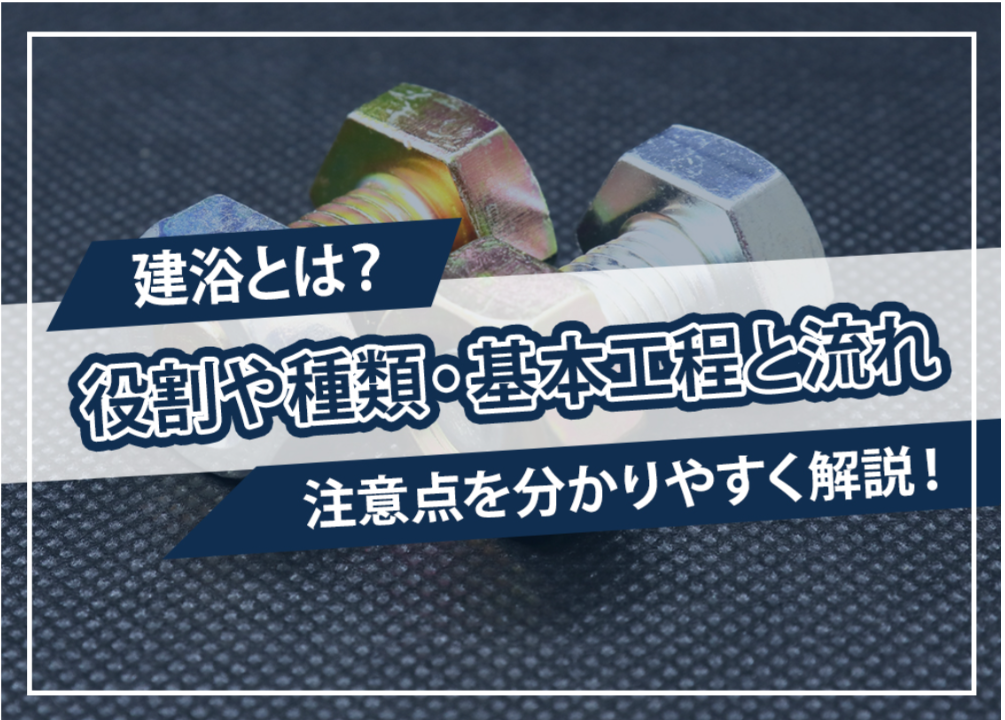
めっき・表面処理液の建浴とは?
建浴とは、 めっき処理や表面処理を行うために、電解槽の中に処理液を調整・充填する準備作業のことです。JIS H 0400:1998では、「電解槽内にめっき浴その他の処理液を作り、電解できるように準備する作業」と定義されています。英語では「initial make-up of electrolytic bath」と表記されます。

建浴の役割
建浴の主な役割は、 めっき処理やその他の表面処理に用いる処理液を適切に準備し、めっき不良や処理ムラの発生を防ぐことにあります。処理液は繰り返し使用される中で、金属イオンや有機物、浮遊物などの不純物が混入しやすく、徐々にバランスが崩れていきます。また、前工程からの液の持ち込みや反応生成物の蓄積も処理液の劣化を招く要因です。
そのため、建浴では各種薬液の濃度やpHを適正な値に整え、処理開始時点での安定した液環境を作ることが重要です。こうした準備を怠ると、密着不良や異物付着、未析出といっためっき不良が発生し、製品の品質に重大な影響を与えかねません。安定した処理品質を維持するには、定期的な液分析やメンテナンスとあわせて、建浴の精度が欠かせない要素となります。
建浴の種類
建浴には、処理液の状態や用途に応じたさまざまな種類があります。
全建浴
新たに処理液をすべて調製し、電解槽へ投入する方法。液の全面交換時に用いられる。
半建浴
処理液の一部のみを入れ替えて再調整する方法。不純物が蓄積した際などに実施される。
調整建浴
使用中の処理液に対して成分を補い、濃度やpHを調整する作業。日常的な管理の一環。
濾過
処理液をフィルターなどで濾過し、浮遊物や沈殿物を除去する方法。液の清浄度を維持。
活性化
処理液の性能が低下した際に、特定の薬剤などで液を再活性化させる手法。
建浴を行うタイミング
めっき液は、長期間使用していると金属成分の偏りや添加剤の分解、不純物の蓄積などにより、性能が徐々に低下します。こうした劣化はめっき皮膜の品質に直結するため、定期的な建浴によって処理液を更新・再調整することが重要です。建浴を行う主なタイミングは以下の通りです。
・新たにめっき槽を設置したとき
・めっき液が古くなり、性状が変化したとき
・めっき仕上がりにむらや不具合が生じたとき
・液中に金属粉や有機物などの不純物が混入したとき
上記の状況では早めに建浴を実施し、処理液を最適な状態に保つことで、安定した品質のめっき加工が可能になります。
建浴に使われる薬品
建浴に用いる薬品は、めっきの種類や処理目的に応じて多岐にわたります。建浴方法には、 単一のめっき液で行う場合に加えて、2種類以上の薬品を組み合わせて処理液を作る方法もあり、それぞれの成分比率や混合順序に注意が必要です。中には、あらかじめ濃度やpHが調整済みの薬液も市販されており、これを使用することで作業の簡略化や品質の安定につながります。
ただし、使用する薬品はめっきの種類(ニッケル、亜鉛、銅など)によって異なり、混合条件や管理方法もそれぞれ異なります。薬品の取扱説明書や仕様書を確認し、適切な手順で建浴を行うことが重要です。
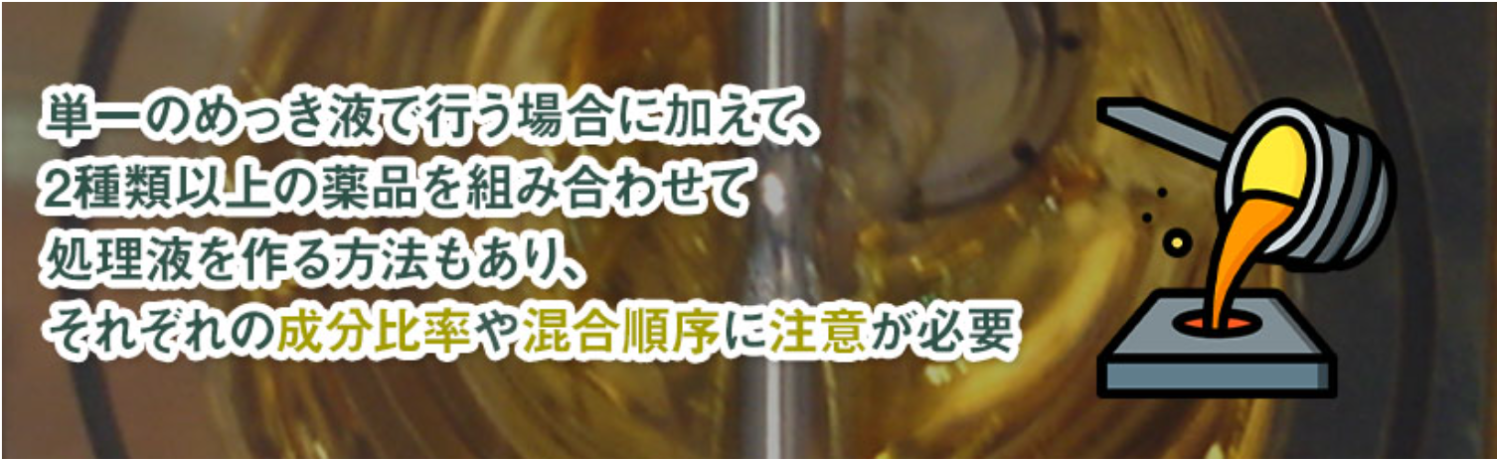
建浴の基本工程と流れ
建浴の工程は、めっき液を新たに調合する「全建浴」を基本として理解しておくと分かりやすくなります。以下では、劣化した液を一度廃棄し、新しい薬品を投入して処理液を作る一連の流れを解説します。
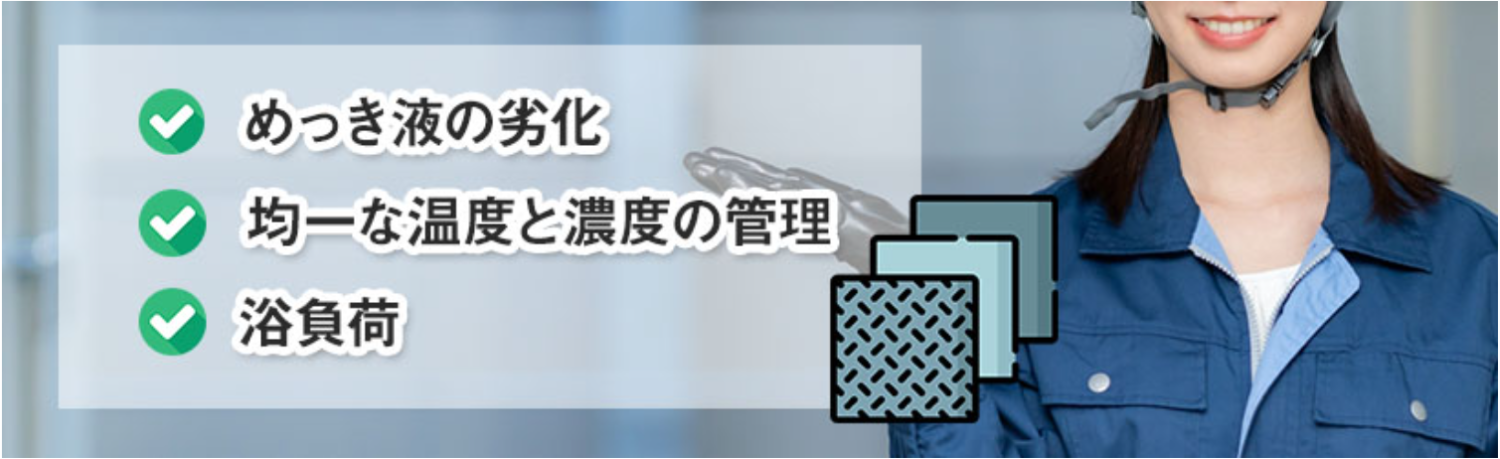
1.劣化した液を廃棄する
全建浴を行う際は、まず既存のめっき液をすべて廃棄する必要があります。使用を重ねるうちに金属成分が減少し、不純物も蓄積されるため、めっき性能が低下していくためです。
めっき液中のニッケルを使い切った時点を「1ターン」と定義し、多くの液では使用できるターン数が決まっています。 限界を超えた液を使い続けると品質不良につながるため、早めの交換が望ましいです。廃液は産業廃棄物として分類され、液性や含有物に応じて、法令に則った処理が求められます。適正に管理されることで、安全かつ安定した運用が可能となるでしょう。
2.薬品を投入して建浴を行う
建浴の工程では、まずめっき槽に適量の水を入れて、必要に応じて加温し、規定された薬品を順に投入します。薬品は1種類だけでなく、複数を組み合わせて使用する場合もあります。これらの薬品は純度や溶解時の反応、副生成物などに注意が必要です。
特に青化亜鉛や酸化亜鉛のように、溶解方法によって生成物が異なる薬品では、浴組成への影響を考慮した取扱いが求められます。 薬品の溶解は別槽で行い、完全に溶けたことを確認した上でめっき槽へ加えるのが原則です。また、化学薬品を取り扱う際は必ず保護具を着用し、安全性にも配慮することが大切です。
建浴時の注意点
建浴を適切に行うためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。以下では、めっき液の劣化や温度・濃度の管理、浴負荷など、建浴時に気をつけたい点を解説します。
①めっき液の劣化
めっき液は、建浴直後から徐々に劣化が始まります。特に無電解ニッケルめっきでは、液中の金属イオンが品物表面以外でも還元・析出してしまう「自己分解」を防ぐため、安定剤の添加が必要です。
安定剤は触媒以外の反応を抑制する働きがあり、濃度を適切に保たないと、ザラつきや皮膜不良の原因になります。鉛などの重金属がかつては主流でしたが、近年は環境規制に対応した有機化合物や鉛代替の無機物が利用されています。安定剤の種類や濃度は、めっき液の種類ごとに最適な範囲があり、その管理が安定しためっきを支える重要な要素と言えます。
②均一な温度と濃度の管理
めっき液の温度や濃度にばらつきがあると、析出する皮膜の厚さや組成に影響し、品質の安定性が損なわれます。 特に無電解ニッケルめっきでは、わずかな温度差や濃度の変化でもリンの含有率が変わり、皮膜特性に差が生じやすくなります。そのため、浴槽全体で均一な温度と濃度を保つことが重要です。
温度維持には電熱器や蒸気加熱などが使用され、槽内を撹拌して成分の偏りを防ぐ工夫も欠かせません。
③浴負荷
無電解ニッケルめっきでは、浴槽内の液量に対して適切な製品の表面積を確保することが重要です。この基準を「浴負荷」と呼びます。
浴負荷が適正でない場合、化学反応が進行しにくくなり、めっきが均一に析出しないことがあります。また、製品が少なすぎると反応が不十分となり、多すぎると撹拌不足や濃度変動により、めっきムラやステップめっきが生じやすくなります。 品質を安定させるには、浴槽サイズに見合った処理量の調整が重要です。
まとめ
建浴とは、めっき処理のために電解槽内に処理液を調整・充填する準備作業です。全建浴、半建浴、調整建浴、濾過、活性化の5種類があり、めっき液の劣化や不純物蓄積時に実施されます。
基本工程は劣化液の廃棄と新薬品の投入で、複数薬品を順次混合します。注意点として、めっき液の劣化防止、均一な温度・濃度管理、適切な浴負荷の維持が重要です。特に無電解ニッケルめっきでは安定剤の添加や自己分解の防止が品質安定のポイントとなります。
めっきに関するお問い合わせはこちら










