めっきのひろば > めっきの剥がれが起きる原因とは
めっきの剥がれが起きる原因とは
はじめに
メッキは装飾性や防食性を高めるために広く利用されている技術ですが、被膜が剥がれると外観の劣化や耐久性の低下を招きます。メッキの剥がれは単なる見た目の問題にとどまらず、製品の寿命を縮め、製造現場にとって深刻な不良となります。
メッキが剥がれる原因は素地のサビや外部からの摩耗、前処理の不十分さなど多岐にわたり、どれも工程管理と密接に関係しています。剥がれや膨れなどのメッキ不良を未然に防ぐには、前処理や素地調整、メッキ液の管理を徹底することが欠かせません。
当記事では、メッキ剥がれの発生要因と防止策、さらに不良が起きた際の原因特定手順を整理し、品質確保に役立つポイントを解説します。メッキ加工に携わっている方は、不良品を防ぐためにもぜひ当記事を参考にしてください。
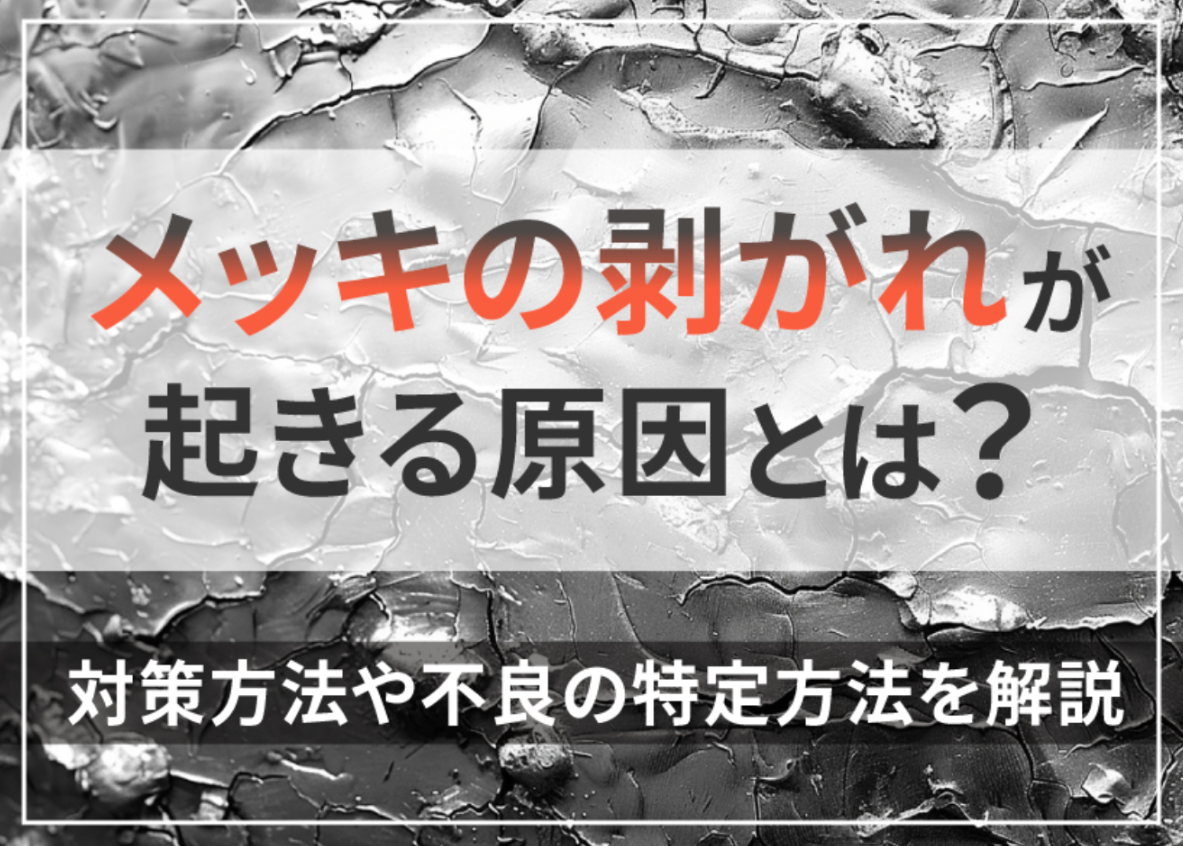
1.メッキの剥がれとは
メッキの剥がれとは、金属の表面に形成されたメッキ被膜が素材から浮き上がり、部分的または全面的に剥離してしまう現象を指します。
メッキは装飾性や防食性、硬度の向上を目的に施されますが、被膜が安定して密着していなければ十分な性能を発揮できません。メッキの剥がれは製品の外観や耐久性を損ない、品質不良につながるため、製造業や金属加工分野では大きな課題です。メッキ剥がれが発生しないよう、原因を正しく把握し、もし発生した場合は再発を防ぐために対策を講じることが不可欠です。
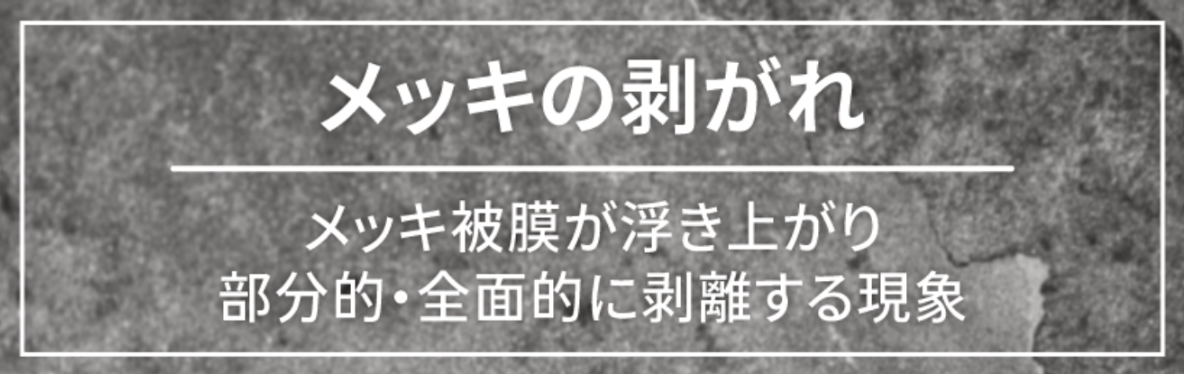
2.メッキの剥がれが起こる原因
メッキの剥がれは、外観の劣化だけでなく防食性能や耐久性の低下にも直結する重大な不良です。主な要因は、素地近くのサビによる膨れ上がり、外部からの摩耗や衝撃による損傷、そして前処理不足による密着不良などが挙げられます。
ここでは、それぞれの具体的な発生メカニズムを解説します。原因別の対策方法も紹介するので、併せて参考にしてください。

①素材に近い部分にサビが発生している
素材に近い層にサビが発生すると、その腐食部分が膨れ上がり、表面のメッキ被膜を押し上げて剥がれを引き起こします。クロームメッキのように一見サビに強い処理でも、下地のニッケル層や鉄素地に水分や酸素が浸入すると腐食が進行します。
また、メッキ被膜には微細なピンホールが存在し、そこから湿気や雨水が浸入することで内部腐食が始まります。この現象は屋外使用や高湿度環境でよく見られます。適切な保護剤でピンホールを塞ぐ処理や、耐食性の高い下地メッキを組み合わせる方法で防止することが可能です。
素地腐食を起点としたメッキの剥がれは長期耐久性を損なうため、設計段階からの材料選定や表面処理条件の見直しが欠かせません。
②硬いものとこすれあった/ぶつかった
メッキ層は金属光沢を帯びるため、一見では頑丈に見えますが、実際には薄い膜であり、硬い物体との接触や衝撃に弱い特性があります。 工具や金属部品との摩擦、輸送時の衝突などで局所的に傷が入ると、その部分から剥がれが広がることがあります。特に薄膜の装飾メッキや延性の高い皮膜では、表面が摩耗すると簡単に下地が露出してしまいます。
対策としては、柔らかい布での清掃や適切な梱包を心がけたり、摩耗や衝撃に耐えられる膜厚やメッキ種類を選定したりすることが挙げられます。使用環境を考慮した設計と取扱いの徹底が、物理的要因による剥がれ防止に直結します。
③脱脂処理や酸洗処理が短かった
メッキ剥がれの大きな要因は、不十分な前処理による密着不良です。
素材表面に油分、酸化皮膜、研磨剤などが残ったままメッキを行うと、被膜が均一に形成されず、後の工程で剥離を招きます。脱脂工程では加工油や防錆油を除去し、酸洗では酸化皮膜を取り除いて表面を活性化させますが、浸漬時間不足や液の劣化によって十分な処理ができない場合があります。また、水洗不足で薬剤が残留すると、膜形成に悪影響を及ぼすこともあります。
工程管理が不十分な状態では、外観上問題がなくても使用中に急速な剥がれが発生します。前処理はメッキの密着性を左右する重要な工程となるので、時間・濃度・液管理を徹底することが品質維持の前提条件です。
3.メッキ剥がれを防ぐための対策方法
メッキ剥がれを防止するには、前処理、素地調整、メッキ液管理の3点を行うことが大切です。いずれかが不十分であると、密着不良や膜の欠陥が生じ、剥がれにつながります。
ここでは、それぞれの対策方法を詳しく解説します。

3-1.十分に前処理を行う
メッキの密着性を左右する最大の要因が前処理です。 素材に付着した油分や酸化皮膜、研磨剤の残渣が除去されないままメッキを行うと、膜が均一に形成されず剥がれの原因となります。
一般的な前処理工程には、脱脂洗浄、酸洗、エッチングがあります。脱脂では切削油や防錆油を除去し、酸洗では黒皮や酸化皮膜を取り除いて表面を活性化させます。エッチングは微細な凹凸を形成し、アンカー効果により密着性を高めます。
適切な前処理を徹底することで、剥がれや膨れのリスクを大幅に低減できます。
3-2.素地を調整する
メッキの品質は、素地そのものの状態に大きく左右されるため、素材の状態をきちんと把握し、整える必要があります。金属素材の場合、バリや深い傷、加工油の残留は密着性低下の原因となります。プラスチックへのメッキでは、成形条件や吸水状態が不良に直結し、膨れや剥がれを引き起こすことがあります。特にエンプラやスーパーエンプラといった難メッキ材では、通常のエッチングでは十分な密着が得られないので、専用の処理方法が求められます。
素地調整を怠ると、後工程でどれだけ管理しても剥がれ不良が発生する可能性が高いため、製造前からの一貫した対応が不可欠です。
3-3.正しくメッキ液を管理する
メッキ液は成膜品質を左右する要となるため、適切な管理が欠かせません。無電解ニッケルメッキなど化学反応を利用する場合、液組成、pH、温度の変動は密着性や膜質に直結します。
また、異物混入や析出不良も剥がれの要因となるので、液の定期的な分析・補正を行い、常に安定した組成を維持しましょう。メッキ液を正しく管理することは、不良の未然防止と長期的な安定生産のためのポイントです。
4.その他のメッキ不良の種類と原因
メッキ不良は剥がれ以外にも多様な現象があり、外観品質だけでなく防食性や機能にも影響します。不良が発生することで、メッキの性能が正しく発揮されなくなるため、現象ごとの発生メカニズムを把握し、工程と設備を点検しましょう。
ここでは、さまざまなメッキ不良について詳しく解説します。
①膨れ
膨れは、メッキ皮膜の一部が素地と密着せず盛り上がる現象です。主な原因は前処理不足で、脱脂不十分による油分残留、酸洗後の水洗不足、マスキング剤の付着などが密着を阻害します。素地側で腐食が進みガスが発生した場合や、止まり穴に薬剤が残留した場合も膨れの発生につながります。
対策としては、脱脂・酸洗・水洗の管理を徹底し、液濃度と浸漬時間を規定範囲に維持すること、複雑形状には超音波洗浄を併用することです。後工程の曲げ負荷で顕在化する膨れもあるため、下地処理と膜厚の最適化も必要です。
②ピット
ピットは、メッキ表面に生じる比較的大きな凹部で、素地まで貫通していない穴を指します。発生要因は、素地表面のむらや傷、前処理のむら、気泡付着、浴中の流れ不足による局所的な析出不良などです。加工工程での砥粒や切粉の付着も起点となります。
対策は、前処理の均一化と異物除去の徹底、治具設計の見直しにより電流分布や流動を安定させること、撹拌とろ過で浴中異物と気泡を抑制することなどです。検査では表面観察だけでなく、断面観察や膜厚分布の測定も行いましょう。下地研磨の品質も上げ、工程内でのクリーン度管理を指標化するのも効果的です。
③ピンホール
ピンホールは、素地や下地層にまで達する微細な貫通孔で、長期的には内部腐食や膨れの起点になります。浴中異物や微小気泡の巻き込みなどによって発生します。
高精度ろ過と連続循環、適切な撹拌などで防止できますが、必要に応じて無電解ニッケルなど緻密な下地を採用し、多層化で貫通孔の進展を抑える工夫も必要です。外観検査と併せ、漏液試験や電気的検査で貫通の有無を確認しましょう。
④割れ(クラック)
割れは、メッキ皮膜に生じる亀裂で、目視可能な線状欠陥として現れます。硬質クロムのように微細クラックを内在するものでも、後加工での機械的負荷や熱処理条件の不適合で割れに発展する場合があります。
対策は、電流密度や温度を適正化して内部応力を抑え、後工程の研削・曲げ条件を見直すことや、必要に応じてベーキングで水素を低減することです。割れが発生した場合は、断面で進展方向と起点を特定し、成膜条件と後処理条件を同時に直す必要があります。
⑤くもり
くもりは、光沢メッキで部分的または全体の光沢が乏しく、白濁した外観になる現象です。原因は、前処理のむらによる核生成密度の差、添加剤バランスの崩れ、浴温や電流密度のばらつき、表面粗さの不均一などで、硫化ガスや皮脂の付着による表面反応でもくもりや変色が進みます。脱脂・酸洗・活性化の安定運用、光沢剤とレベラーの分析補正、温度と電流の均一化、製品接触や保管資材の見直しなどで対策が可能です。意匠品では下地研磨を高番手まで仕上げ、膜の平滑性を確保すると改善します。
⑥ザラ
ザラは、表面に微小な突起が点在し粗く感じる状態で、浴中の固体浮遊物や素地由来の切粉・研磨粒子の巻き込みが主な原因です。循環ラインのろ過性能不足や槽内沈積、治具や搬送装置の清掃不良も寄与します。
ザラは、ろ過精度の向上と定期的なバックウォッシュ、槽底清掃、前処理からの異物持ち込みを制限することで防げます。意匠低下だけでなく局部的な腐食の原因にもなり得るため、粒度解析で異物源を特定し、工具・研磨材の管理と交換周期を明確化します。
⑦しみ
しみは、皮膜に染み状の汚れや色むらが残る現象で、梨地など粗面で目立ちやすい傾向があります。脱脂不足や水洗不足による薬剤・油分の残留、乾燥工程での水跡などが原因です。
対策を行う際は、処理後のリンス段数と水質の見直し、純水仕上げと乾燥条件の最適化、素手接触の回避、保管材の選定を行いましょう。発生後は軽度ならば洗浄で回復しますが、化学反応を伴う変色は再加工が必要になるため、工程初期での検知が大切です。
⑧焼け
焼けは、過大な電流密度や不適切な温度管理で粗い結晶が形成され、暗灰色で光沢の乏しい外観になる現象です。電極配置や治具設計が不適切で先端部や角部に電流が集中した場合や、添加剤枯渇・浴組成の不安定化でも発生します。
対策としては、電流密度の上限管理と電源のリップル低減、補助電極やシールドでの電流分散、浴温の安定化、添加剤の定期分析と補正などが有効です。流動が不足すると境膜が厚くなり極端な過電位が生じるため、撹拌と循環を適正化しましょう。
5.メッキ不良の原因を特定する手順
メッキ不良の特定は、現場の状況把握、再現確認、工程条件の是正という順で進めると効率的です。まず、発生箇所や工程を絞り込み、過去事例と照合して仮説を立てるところから始めましょう。
ここでは、原因特定のための手順をそれぞれ解説します。
1.まず現場を確認する
最優先で行わなければならないのは、現場での一次情報収集です。発生時刻、治具やラックの状態、換気や撹拌、液量・液温、電流密度、搬送経路、水洗水の清浄度などを時系列で記録しておきましょう。現象別に位置関係を整理すると、換気ミストの付着やアノードスライムの流出、止まり穴の薬剤残留など、現場固有の要因を捉えやすくなります。
剥離の層位も重要で、第1層の剥離か、層間剥離かで原因工程が異なります。素手接触や保管資材による汚染も観察しなければならない対象です。現場で写真とサンプルを採取し、対照群と併せて保存することで、後工程の分析精度が高まります。
2.過去の不良事例を確認する
同種の不良は類似条件で再発する傾向があるため、社内データベースを検索し、現象、起点、対策、再発有無を照合しましょう。たとえば硫酸銅系のザラでは、空気撹拌不足、塩化物イオン増、ろ過不足、過大電流などがよくある要因です。
素材を変更したときや金型を改修したとき、薬剤によるロット差も再発の要因となるため、図番や治具構成、薬液ロット、設備点検履歴を横断的に確認します。過去の事例と結びつけることにより仮説の優先度を付け、検証計画に反映することも可能です。
過去の事例があまりない場合には、外部規格や業界事例を参照し、評価手順と判定基準を補完する必要があります。
3.不良要因を分析する
仮説がある程度立てられた後は、成形・前処理・メッキ・仕上げの各工程で要因分析を行います。
成形では残留応力、吸水、離型剤の残留を確認し、前処理では脱脂力、酸洗の活性度、水洗の導電率や油分濃度を測定します。メッキ工程では浴組成、pH、温度、添加剤、電流密度、流動、ろ過状況を分析し、ハルセルや試験片で傾向を掴みます。仕上げでは外観検査に加え、断面観察、膜厚分布、付着性試験、熱衝撃などでメカニズムを特定します。
層位判定や異物同定には断面EDXや表面分析が有効です。測定結果はトレーサビリティと紐づけ、ばらつきの発生源を明確化します。
4.不良の再現性をチェックする
要因候補ごとに条件を1つずつ変更し、再現試験を実施して再現性をチェックします。電流密度、処理時間、浴温、撹拌、ろ過、洗浄水の水質など、影響度の高い因子から順に検証しましょう。止まり穴や複雑形状はダミー品で模擬し、薬剤残留や気泡付着を可視化します。
不良の再現に成功した場合は、臨界条件を特定し管理幅を定義します。再現できない場合は、交互作用や素材ロット差を疑い、二因子試験や別ロットで再確認しましょう。判定は外観のみでなく、付着性や断面での層位確認まで含め、再現性と再発性の両面から検証することが大切です。
5.処理工程を改善する
特定した起点に対して、工程・設備・管理の各層で恒久対策を実装します。
成形では乾燥条件や離型剤の選定、金型や冷却条件の見直しで汚染や応力を抑制します。前処理では脱脂剤濃度と浸漬時間、酸洗の活性度、水洗段数と水質基準を明文化し、超音波や循環で難形状への適用性を高めます。メッキでは浴組成の日次分析、添加剤補正、電流分散用の補助電極やシールド、ろ過精度と清掃周期の管理を行います。仕上げと保管では接触防止、資材の見直し、検査強化を行い、標準書と点検表を更新しましょう。
修正した後は監視指標を設定し、再発防止を確認することで不良を防ぎます。
まとめ
メッキ剥がれは見た目の影響だけでなく、機能や信頼性を大きく損なう要因となります。メッキが剝がれてしまう主な原因は素地腐食や物理的損傷、前処理不足に分類でき、それぞれ適切な管理や設計で防止することができます。
メッキの不良には、膨れやピンホール、くもりなどさまざまな種類があるため、工程ごとの点検と改善が欠かせません。不良が発生したときは現場確認から要因分析、再現試験、工程改善までの流れを踏み、再発防止に努めましょう。
品質を安定させるためには、工程全体を通じた一貫した管理体制とデータに基づく改善が必要です。日常の記録や分析を積み重ね、長期的に信頼性の高い製品供給を実現しましょう。
めっきに関するお問い合わせはこちら










