めっきのひろば > かじりとは?②
かじりとは?②
4.かじりを起こしやすい金属の種類
金属のかじりはあらゆる金属で発生する可能性がありますが、特性によって発生しやすい金属が存在します。特に、延性が高く表面硬度が低い金属や、酸化皮膜を有する金属は、摩擦熱や高荷重が加わることで凝着を起こしやすくなります。
ここでは、かじりやすい代表的な3種類の金属について、それぞれの特徴と留意点を解説します。

1.ステンレス
ステンレス鋼は、かじりを起こしやすい金属の1つです。特に オーステナイト系は、延性が高く熱伝導率が低いため、摩擦熱がこもりやすく、かじりを起こしやすい特性を持っています。加えて、自己修復性のある酸化被膜(不動態皮膜)を持つことで、潤滑の役割も果たしますが、高荷重や繰り返し摺動によって皮膜が破壊されると、金属同士の直接接触が起こります。
ステンレス同士でねじ締結を行う場合などでは、熱伝導率の低さにより摩擦熱が局所にこもり、膨張や焼き付きにつながることがあります。異なるステンレスグレードの組み合わせや、表面への潤滑剤塗布、コーティング処理などを行って対策しましょう。
2.アルミ
アルミニウムは柔らかく、延性が高い金属であるため、摩擦によるかじりが発生しやすい金属として知られています。特にアルミ同士の接触では表面が容易に傷つきやすく、摩擦熱の蓄積によって冷間溶着が起きることがあります。
また、アルミ表面の酸化皮膜は薄く損傷しやすいため、酸化被膜が壊れるとすぐに金属同士の接触が始まり、凝着摩耗が進行します。対策としては、潤滑剤の使用や圧力の適正化、陽極酸化処理などの表面強化処理を施すことが挙げられます。軽量化が求められる場面ではアルミは有用ですが、かじりのリスクを考慮した設計が必要です。
3.チタン
チタンは軽量かつ強度に優れ、耐食性にも優れる金属ですが、かじりやすい性質を持っています。特に純チタンは表面硬度が低く、摺動や締結の際に摩擦係数が高くなるため、金属面の接着が起こりやすくなります。また、熱伝導率が低いため、接触面で発生した摩擦熱が外部に逃げにくく、熱が蓄積して凝着を助長します。
かじりを防ぐには、チタン合金の使用や、窒化処理などの表面硬化処理を施しましょう。また、ねじやナットの締結時には潤滑剤を活用することが大切です。
5.かじりの予防法
金属のかじりは、設備や機器の寿命を著しく縮める重大なトラブルの1つです。しかし、適切な材料選定や表面処理、運用方法を実施することで、その発生を防げます。ここでは、現場で実践できる具体的なかじりの予防策について紹介します。
1.摺動部には同じ素材を使わない
かじりを防ぐ基本的な方法の1つが、摺動部に異なる材質を使用することです。 金属同士の組み合わせにおいて、同種金属は凝着摩耗が起こりやすく、特にステンレスやアルミニウムなど延性の高い金属同士ではかじりが発生しやすくなります。冶金的性質の異なる金属を組み合わせることで、金属間の冷間圧接を抑制し、かじりリスクを軽減できます。
たとえば、ステンレス部品には真鍮や青銅、アルミには鋼材など、材質の違いによる冶金結合の抑制が効果的です。部品設計時には、接触する材料の選定に注意を払いましょう。
2.潤滑剤を表面に塗る
潤滑剤の使用は、かじり対策として広く採用されている基本的な方法です。 潤滑剤は金属表面間の摩擦を軽減し、摩擦熱の上昇を抑えることで、凝着や摩耗の発生を防ぎます。グリースやオイル、二硫化モリブデン、PTFEを含む潤滑剤など、用途や使用環境に応じた適切な種類を選びましょう。
ただし、潤滑剤は流出する可能性があるため、定期的な再塗布や塗布量の管理が必要です。狭い摺動部では、過剰な潤滑により締結トルクに影響を与えることもあるため、使用時には適切な管理が求められます。
3.表面加工を施す
かじりの防止には、表面処理による対策も有効です。 表面加工により、摩擦係数を低減し、金属間の凝着を抑制できます。表面処理により、金属表面に硬質のバリア層が形成され、直接接触を防げます。
締結部品や高荷重部品においては、繰り返し使用しても効果が持続する耐摩耗性の高い処理が望まれます。
4.負荷のかかりすぎを避ける
過度な荷重は、摩擦熱の発生を促進し、かじりの直接的な要因となります。特にねじやボルトの締結部においては、締め付けトルクの過剰により接触圧が高まり、金属面の局所的な温度上昇を引き起こします。その結果、冷間圧接や表面損傷が発生するおそれがあります。
かじり防止のためには、適正トルクでの締結を徹底しましょう。トルクレンチやデジタル制御機器を活用し、荷重の過大投入を防ぐことが求められます。また、構造設計の段階で応力集中を回避する工夫も大切です。
5.汚れや傷がないかメンテナンスで確認
定期的な点検とメンテナンスは、かじりを未然に防ぐために欠かせない作業です。金属部品の表面に傷や汚れが付着していると、摩擦の増加や酸化被膜の破壊を引き起こし、かじりの発生要因になります。また、異物が接触面に入り込むと局所的な摩耗を助長します。
運用中の部品は定期的に清掃し、必要に応じて潤滑剤を再塗布することが望まれます。摩耗の兆候が見られた場合は、早期に部品を交換するなどの対応を行いましょう。
6.かじりの発生を防ぐのに効果的なめっき
かじり対策として効果的な方法の1つが、金属表面に適切なめっきを施すことです。特に注目されるのが、インジウムめっきと硬質銀めっきです。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、使用環境や用途に応じて高い耐かじり性能を発揮します。
インジウムめっきは、156℃という低融点を持つ軟質金属です。柔軟性が高く、優れたシール性と耐アルカリ性を兼ね備えており、摺動時の金属間の密着を緩和し、摩擦や冷間溶着を防止します。航空宇宙分野でも利用されることが多く、高精度な金属接合に適しています。
一方、硬質銀めっきは、高硬度(Hv155程度)の皮膜を持ち、従来の銀めっきよりも優れた耐摩耗性と摺動性を発揮します。特に電気自動車や産業用コネクターなど、高頻度の抜き差しが行われる場面に適しており、かじりに強い表面を形成します。
これらのめっき処理を適切に選定・実施することで、金属部品の信頼性と耐久性を大幅に向上させることが可能です。
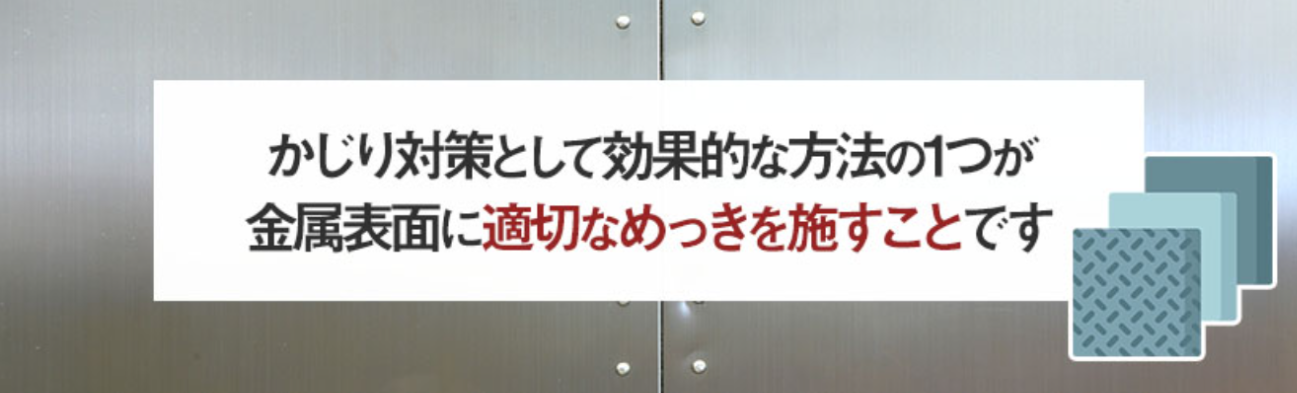
まとめ
金属のかじりは、摩擦や圧力、環境条件などが複雑に絡み合って発生するトラブルです。特にステンレスやアルミ、チタンなどはかじりやすい金属として知られており、部品の設計や運用方法に注意を払う必要があります。かじりの防止には、異種材料の組み合わせや潤滑剤の活用、表面処理、適正な締結トルクの管理など、いくつかの基本的な対策が有効です。
さらに、インジウムめっきや銀めっきといった表面処理技術を活用することで、かじりに対する耐性を一段と高められます。設計段階から予防を意識し、部品寿命や安全性を確保するためにも、金属のかじりについて正しく理解し、実践的な対策を講じましょう。
耐かじり性を持つめっきのお問い合わせはこちらから










