めっきのひろば > 犠牲防食とは?
犠牲防食とは?
はじめに
鉄や鋼材を扱う現場において「気づいたらサビが進行していた」というケースは少なくありません。塗装や被覆で一時的に防げても、わずかな傷や隙間から赤サビが広がり、耐久性が落ちることに悩む方も多いでしょう。こうした課題を解決する方法の1つが「犠牲防食」です。鉄よりも先に腐食しやすい亜鉛をめっきすることで、鉄の素地を守る仕組みです。
ただし、高温多湿の環境では犠牲防食が反対に作用し、鉄の腐食を進めてしまう「逆転現象」が起こるリスクもあります。当記事では、犠牲防食の基本原理や代表的な素材、逆転現象とその防止策を解説します。犠牲防食の仕組みを理解すれば、建材や設備をより長持ちさせ、コストやメンテナンスの負担を減らす判断に役立つでしょう。
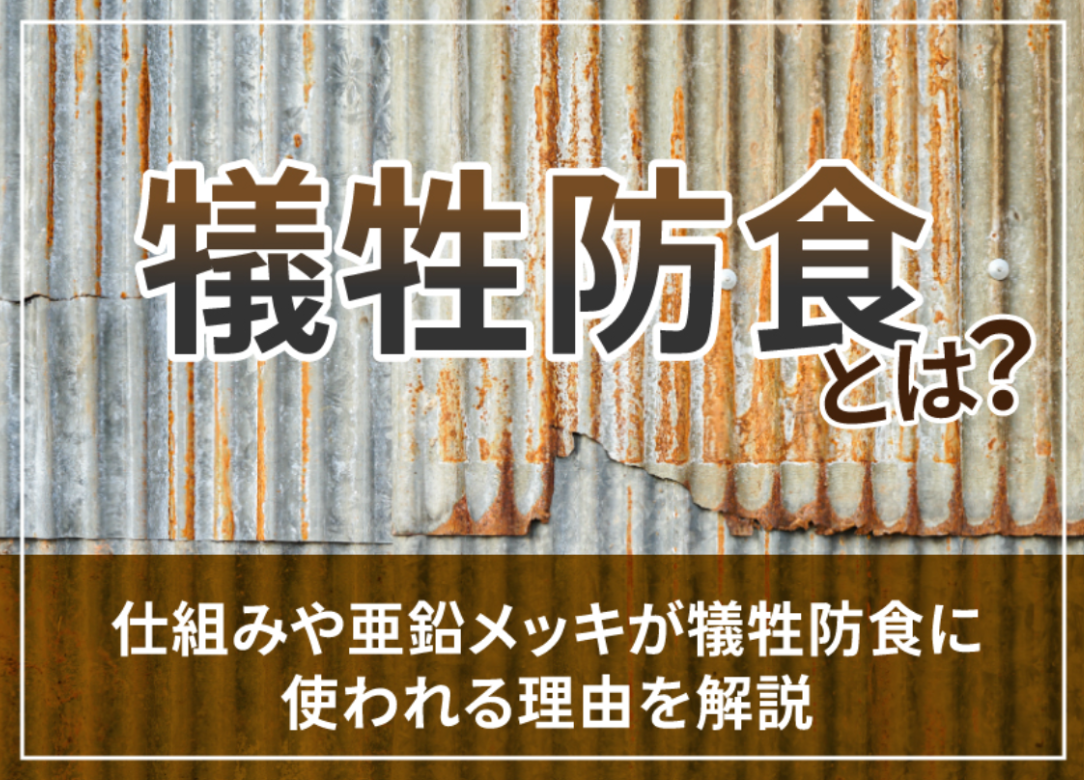
犠牲防食とは
犠牲防食とは、金属を腐食から守るための代表的な防食方法の1つです。鉄は丈夫で広く利用される素材ですが、水や空気に触れると赤サビが発生し、耐久性を損ないます。表面を樹脂などで被覆すれば初期状態では保護できますが、被覆に欠陥やキズがあると、露出した鉄が急速に腐食してしまいます。
そこで、鉄のサビ防止に有効なのが、亜鉛めっきに代表される犠牲防食です。鉄よりもイオン化しやすい亜鉛を表面にめっきすると、傷がついて鉄が露出しても、亜鉛が先に溶け出して犠牲的に腐食し、鉄の腐食を防止します。このように、 めっきが自らを犠牲にして素地の金属を守る仕組みを「犠牲防食」と呼び、トタンやプレメッキ鋼管などの幅広い素材で利用されています。
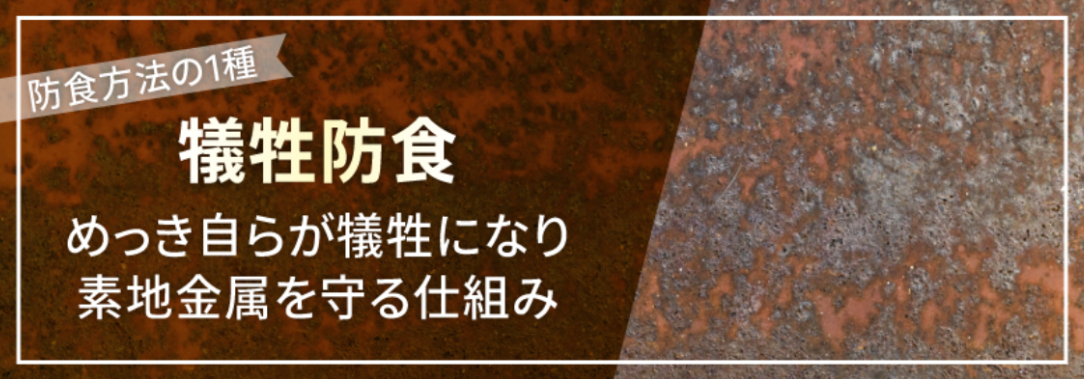
金属が腐食するメカニズム
金属の腐食は、環境との化学反応や電気化学的反応によって金属が劣化・破壊される現象です。通常、金属表面には大気中の酸素によって極薄の酸化皮膜が形成されますが、水分や雨水、付着した汚染物質などにより皮膜が破壊されると、内部に向かって腐食が進行します。
腐食が起こるには、 酸化剤(酸素や水素イオン)、腐食されやすい金属、水の3つの条件が重なる必要があります。腐食形態には、鉄が大気中で錆びて表面全体に一様に進行する「均一腐食」と、部品の局所に発生して深刻な損傷をもたらす「局部腐食」があり、さらに粒界腐食や孔食、すきま腐食、応力腐食割れなどの多様な形態が存在します。
仕組み|亜鉛メッキが使われる理由
犠牲防食の代表例として広く使われているのが亜鉛めっきです。鉄は、水や酸素に触れると錆びてしまいます。しかし、 鉄よりもイオン化傾向の大きい亜鉛を表面にめっきすることで、鉄が露出しても先に亜鉛が酸化して電子を放出し、鉄を腐食から守ります。つまり、亜鉛が「犠牲陽極」となり、自らを犠牲にして鉄を防食する仕組みです。
一般的な塗装は傷が入ると鉄が錆びてしまいますが、亜鉛めっきではその部分が局部電池となり、亜鉛層が優先的に溶け出す犠牲的防食作用によってサビの進行を抑えられます。この電気化学的な働きが「電気防食」の一種であり、亜鉛が選ばれる理由です。
一方で、鉄にニッケルなどイオン化傾向の小さい金属をめっきしても、素地金属の鉄のほうが先に腐食してしまうため、防食効果は得られません。こうした仕組みから、亜鉛めっきはトタンや鋼管などのさまざまな素材に利用され、防サビ技術として欠かせない存在となっています。
三ツ矢の亜鉛めっきはこちら
犠牲防食の仕組みを利用した素材
犠牲防食の仕組みは、建築資材や日用品など、身近な金属素材にも幅広く応用されています。代表的なものにトタン・ブリキ・ガルバリウムがあり、それぞれの特性を生かして鉄をサビから守り、耐久性を高めています。ここからは、それぞれの素材について具体的に解説します。
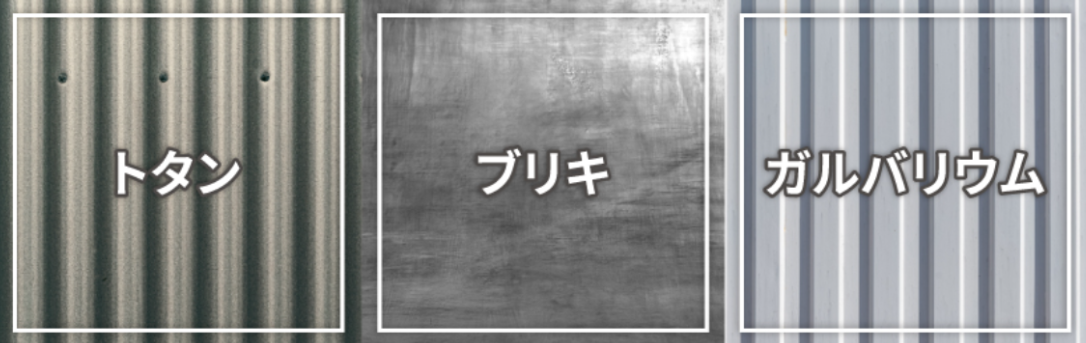
①トタン
トタンは、鉄板に亜鉛をめっきした「亜鉛めっき鋼板」で、もっとも身近な犠牲防食の応用例です。仮に表面に傷が入って鉄が露出しても、亜鉛が優先的に腐食することで鉄を守る仕組みになっています。大正時代から安価で施工しやすい屋根材として普及し、特に高度経済成長期には住宅や公共建築で広く採用されました。
トタン屋根は軽量で耐震性に優れることから日本の気候や建築事情に適しており、コストパフォーマンスも高い点が魅力です。一方で、耐久性や断熱性に課題があり、定期的なメンテナンスや追加の断熱対策が求められる素材でもあります。
②ブリキ
ブリキは、鉄板の表面にスズをめっきした素材で、鉄の加工しやすさとスズの耐食性・美しい光沢を兼ね備えています。スズは鉄よりもイオン化傾向が小さく錆びにくいため、缶詰やおもちゃ、広告看板など幅広く利用されてきました。
しかし、犠牲防食の働きを持つトタンとは異なり、表面に傷がついて鉄素地が露出すると、鉄のほうが先に腐食してしまうという弱点があります。そのため、現在では看板用途ではアルミやステンレスに取って代わられ、ブリキは主に食品用缶詰や容器に利用される素材となっています。
③ガルバリウム
ガルバリウム鋼板は、アルミ55%・亜鉛43.4%・シリコン1.6%から成る合金でめっきされた鋼板です。アルミの耐食性と亜鉛特有の犠牲防食作用を組み合わせた二重の保護機能により、トタンに比べて格段に錆びにくく、長寿命を実現しています。
さらに、軽量で耐震性にも優れているため、住宅や商業施設の金属外装材の主流となっています。一方で、「凹みに弱い」「断熱性や遮音性が劣る」といった課題もあるため、断熱材一体型やカバー工法によって補強するケースが一般的です。
犠牲防食の逆転現象
犠牲防食の逆転現象とは、本来は鉄を守るはずの犠牲陽極である亜鉛が、反対に鉄の腐食を促進してしまう現象のことです。通常、亜鉛めっきは紫外線や雨風といった過酷な環境でも高い防食性能を発揮します。
しかし、特定の条件下では、腐食効果が損なわれることがあります。その結果、犠牲防食が反対に作用し、鉄の腐食が進行してしまうのです。
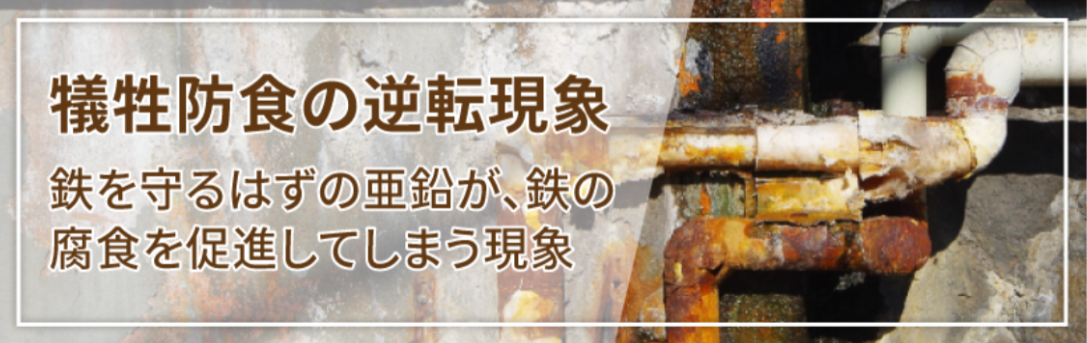
犠牲防食の逆転現象が起こりやすい環境
犠牲防食の逆転現象は、特に高温多湿の環境で発生しやすいとされています。たとえば、夏場に直射日光を受けた屋外の水道管や、常に温水が流れるパイプは、表面に水分が付着しやすく温度も高くなるため注意が必要です。
農業用ビニールハウスの巻取り軸も典型例の1つで、濡れたシートを巻き取った部分に水が溜まり、夏場には表面温度が100℃近くまで上昇することがあります。このような高温多湿の条件下では、 亜鉛めっきの電気化学的性質が変化して防食作用がうまく機能せず、鉄の腐食が進行してしまいます。
犠牲防食の逆転現象を防止する方法
犠牲防食の逆転現象を完全に避けるために、常に理想的な環境条件に保つのは現実的に困難です。しかし、 追加の防食対策を講じることで、犠牲防食の逆転現象の発生リスクを減らすことが可能です。たとえば、「亜鉛めっき層の保護や補修を定期的に行い、湿気や酸化物を除去する」「適切な塗装皮膜やコーティングを施す」などが効果的です。
また、高耐食加工を施した製品を採用するのも有効な方法です。初期費用は高くなる場合がありますが、錆びにくいため交換や補修の手間が減り、長期的にはコスト削減にもつながるでしょう。
まとめ
犠牲防食は、鉄の表面に鉄よりもイオン化しやすい亜鉛をめっきすることで、亜鉛が犠牲的に先に腐食し、鉄をサビから守る仕組みです。トタンやブリキ、ガルバリウムなど、身近な素材は犠牲防食効果の原理を応用しており、建築や日用品の分野で広く活用されています。
ただし、高温多湿の環境では犠牲防食の作用がうまく働かず、かえって鉄の腐食が進んでしまう「逆転現象」が起こるリスクもあります。犠牲防食の逆転現象を防ぐ方法には、追加の防食対策や高耐食加工製品の利用が挙げられます。犠牲防食の仕組みと注意点を理解することは、設備や建材を長持ちさせ、メンテナンスの手間やコストを減らす上で重要です。ぜひ実際の現場や製品選びに生かし、長期的に安心できる環境づくりに役立ててください。
亜鉛めっきに関するお問い合わせはこちら










